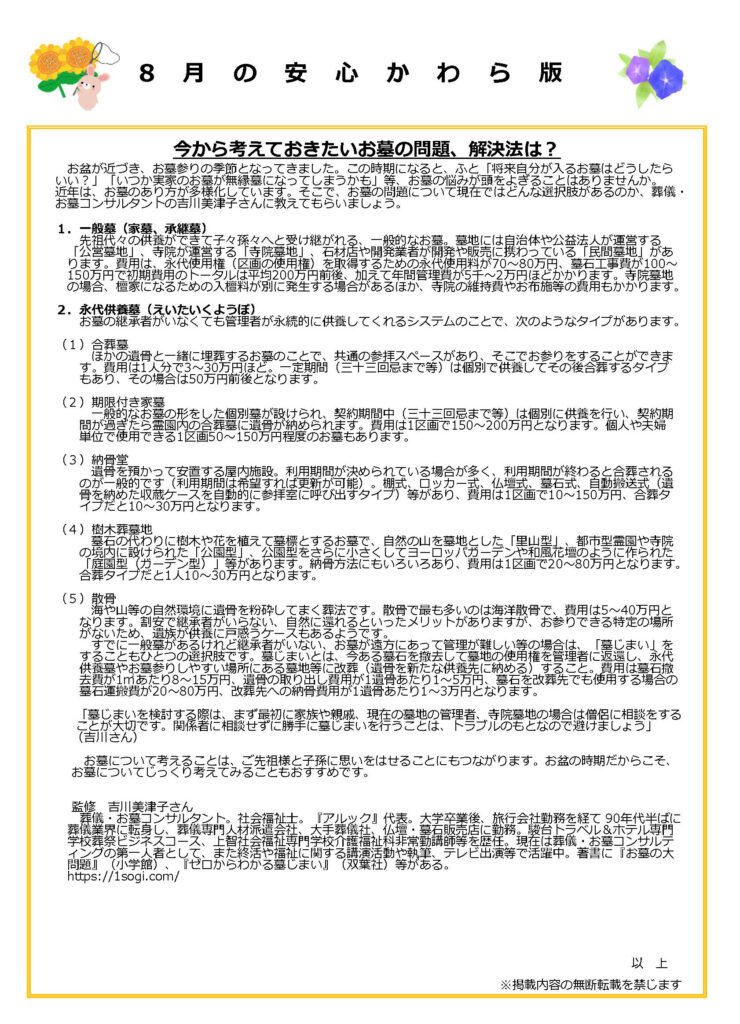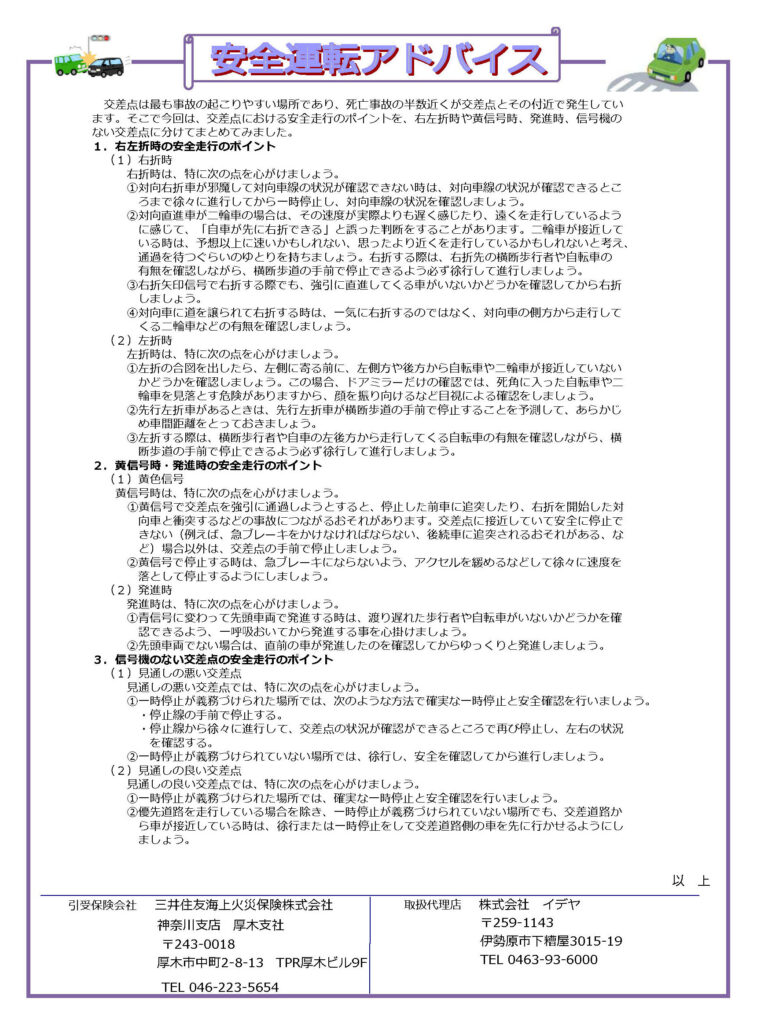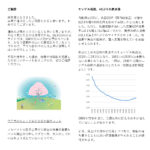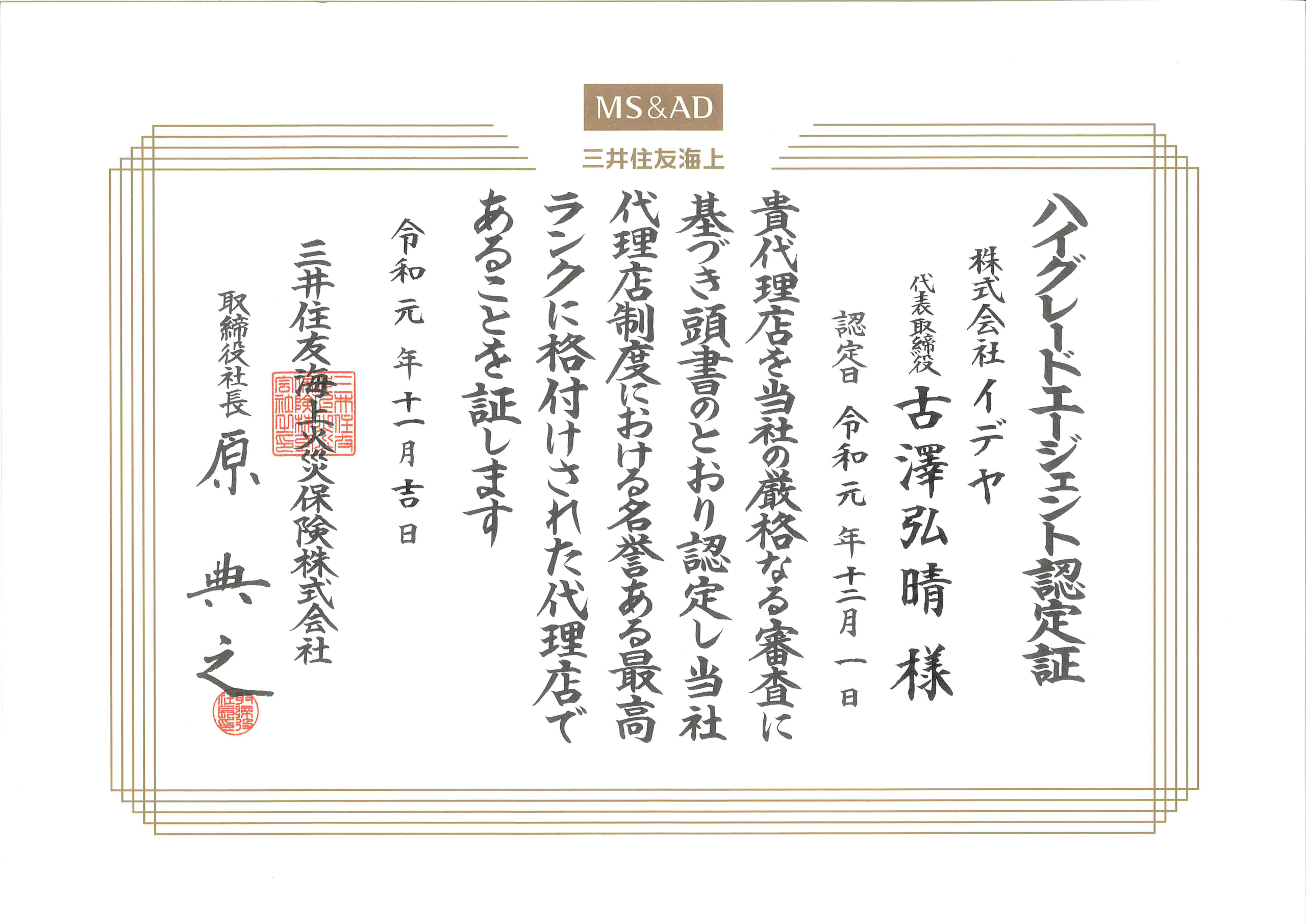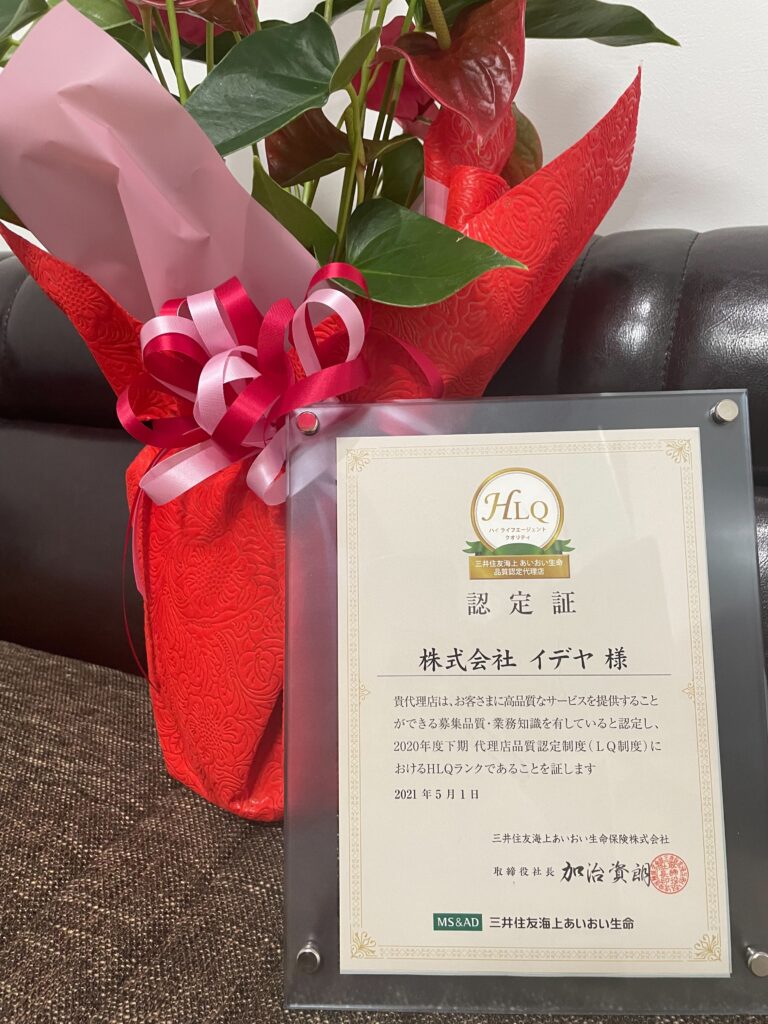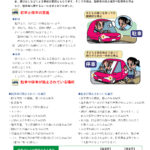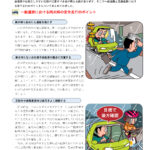2022年8月の安心かわら版
今から考えておきたいお墓の問題、解決法は?
お盆が近づき、お墓参りの季節となってきました。この時期になると、ふと「将来自分が入るお墓はどうしたらいい?」「いつか実家のお墓が無縁墓になってしまうかも」等、お墓の悩みが頭をよぎることはありませんか近年は、お墓のあり方が多様化しています。そこで、お墓の問題について現在ではどんな選択肢があるのか、葬儀・お墓コンサルタントの吉川美津子さんに教えてもらいましょう
一般墓(家墓、承継墓)
先祖代々の供養ができて子々孫々へと受け継がれる、一般的なお墓。墓地には自治体や公益法人が運営する「公営墓地」、寺院が運営する「寺院墓地」、石材店や開発業者が開発や販売に携わっている「民間墓地」があります。費用は、永代使用権(区画の使用権)を取得するための永代使用料が70~80万円、墓石工事費が100~150万円で初期費用のトータルは平均200万円前後、加えて年間管理費が5千~2万円ほどかかります。寺院墓地の場合、檀家になるための入檀料が別に発生する場合があるほか、寺院の維持費やお布施等の費用もかかります。
永代供養墓(えいたいくようぼ)
お墓の継承者がいなくても管理者が永続的に供養してくれるシステムのことで、次のようなタイプがあります
(1)合葬墓
ほかの遺骨と一緒に埋葬するお墓のことで、共通の参拝スペースがあり、そこでお参りをすることができます。費用は1人分で3~30万円ほど。一定期間(三十三回忌まで等)は個別で供養してその後合葬するタイプもあり、その場合は50万円前後となります
(2)期限付き家墓
一般的なお墓の形をした個別墓が設けられ、契約期間中(三十三回忌まで等)は個別に供養を行い、契約期間が過ぎたら霊園内の合葬墓に遺骨が納められます。費用は1区画で150~200万円となります。個人や夫婦単位で使用できる1区画50~150万円程度のお墓もあります
(3)納骨堂
遺骨を預かって安置する屋内施設。利用期間が決められている場合が多く、利用期間が終わると合葬されるのが一般的です(利用期間は希望すれば更新が可能)。棚式、ロッカー式、仏壇式、墓石式、自動搬送式(遺骨を納めた収蔵ケースを自動的に参拝室に呼び出すタイプ)等があり、費用は1区画で10~150万円、合葬タイプだと10~30万円となります
(4)樹木葬墓地
墓石の代わりに樹木や花を植えて墓標とするお墓で、自然の山を墓地とした「里山型」、都市型霊園や寺院の境内に設けられた「公園型」、公園型をさらに小さくしてヨーロッパガーデンや和風花壇のように作られた「庭園型(ガーデン型)」等があります。納骨方法にもいろいろあり、費用は1区画で20~80万円となります合葬タイプだと1人10~30万円となります
(5)散骨
海や山等の自然環境に遺骨を粉砕してまく葬法です。散骨で最も多いのは海洋散骨で、費用は5~40万円となります。割安で継承者がいらない、自然に還れるといったメリットがありますが、お参りできる特定の場所がないため、遺族が供養に戸惑うケースもあるようです
すでに一般墓があるけれど継承者がいない、お墓が遠方にあって管理が難しい等の場合は、「墓じまい」をすることもひとつの選択肢です。墓じまいとは、今ある墓石を撤去して墓地の使用権を管理者に返還し、永代供養墓やお墓参りしやすい場所にある墓地等に改葬(遺骨を新たな供養先に納める)すること。費用は墓石撤去費が1㎡あたり8~15万円、遺骨の取り出し費用が1遺骨あたり1~5万円、墓石を改葬先でも使用する場合の墓石運搬費が20~80万円、改葬先への納骨費用が1遺骨あたり1~3万円となります
「墓じまいを検討する際は、まず最初に家族や親戚、現在の墓地の管理者、寺院墓地の場合は僧侶に相談をすることが大切です。関係者に相談せずに勝手に墓じまいを行うことは、トラブルのもとなので避けましょう」(吉川さん)
お墓について考えることは、ご先祖様と子孫に思いをはせることにもつながります。お盆の時期だからこそ、お墓についてじっくり考えてみることもおすすめです。
監修 吉川美津子さん
葬儀・お墓コンサルタント。社会福祉士。『アルック』代表。大学卒業後、旅行会社勤務を経て90年代半ばに葬儀業界に転身し、葬儀専門人材派遣会社、大手葬儀社、仏壇・墓石販売店に勤務。駿台トラベル&ホテル専門学校葬祭ビジネスコース、上智社会福祉専門学校介護福祉科非常勤講師等を歴任。現在は葬儀・お墓コンサルティングの第一人者として、また終活や福祉に関する講演活動や執筆、テレビ出演等で活躍中。著書に『お墓の大問題』(小学館)、『ゼロからわかる墓じまい』(双葉社)等がある
https://1sogi.com/
安全運転アドバイス
交差点は最も事故の起こりやすい場所であり、死亡事故の半数近くが交差点とその付近で発生しています。そこで今回は、交差点における安全走行のポイントを、右左折時や黄信号時、発進時、信号機のない交差点に分けてまとめてみました
右左折時の安全走行のポイント
(1)右折時
右折時は、特に次の点を心がけましょう
①対向右折車が邪魔して対向車線の状況が確認できない時は、対向車線の状況が確認できるところまで徐々に進行してから一時停止し、対向車線の状況を確認しましょう
②対向直進車が二輪車の場合は、その速度が実際よりも遅く感じたり、遠くを走行しているように感じて、「自車が先に右折できる」と誤った判断をすることがあります。二輪車が接近している時は、予想以上に速いかもしれない、思ったより近くを走行しているかもしれないと考え、通過を待つぐらいのゆとりを持ちましょう。右折する際は、右折先の横断歩行者や自転車の有無を確認しながら、横断歩道の手前で停止できるよう必ず徐行して進行しましょう
③右折矢印信号で右折する際でも、強引に直進してくる車がいないかどうかを確認してから右折しましょう
④対向車に道を譲られて右折する時は、一気に右折するのではなく、対向車の側方から走行してくる二輪車などの有無を確認しましょう
(2)左折時
左折時は、特に次の点を心がけましょう
①左折の合図を出したら、左側に寄る前に、左側方や後方から自転車や二輪車が接近していないかどうかを確認しましょう。この場合、ドアミラーだけの確認では、死角に入った自転車や二輪車を見落とす危険がありますから、顔を振り向けるなど目視による確認をしましょう
②先行左折車があるときは、先行左折車が横断歩道の手前で停止することを予測して、あらかじめ車間距離をとっておきましょう
③左折する際は、横断歩行者や自車の左後方から走行してくる自転車の有無を確認しながら、横断歩道の手前で停止できるよう必ず徐行して進行しましょう
黄信号時・発進時の安全走行のポイント
(1)黄色信号
黄信号時は、特に次の点を心がけましょう
①黄信号で交差点を強引に通過しようとすると、停止した前車に追突したり、右折を開始した対向車と衝突するなどの事故につながるおそれがあります。交差点に接近していて安全に停止できない(例えば、急ブレーキをかけなければならない、後続車に追突されるおそれがある、など)場合以外は、交差点の手前で停止しましょう
②黄信号で停止する時は、急ブレーキにならないよう、アクセルを緩めるなどして徐々に速度を落として停止するようにしましょう
(2)発進時
発進時は、特に次の点を心がけましょう
①青信号に変わって先頭車両で発進する時は、渡り遅れた歩行者や自転車がいないかどうかを確認できるよう、一呼吸おいてから発進する事を心掛けましょう
②先頭車両でない場合は、直前の車が発進したのを確認してからゆっくりと発進しましょう
信号機のない交差点の安全走行のポイント
(1)見通しの悪い交差点
見通しの悪い交差点では、特に次の点を心がけましょう
①一時停止が義務づけられた場所では、次のような方法で確実な一時停止と安全確認を行いましょう・停止線の手前で停止する・停止線から徐々に進行して、交差点の状況が確認ができるところで再び停止し、左右の状況を確認する
②一時停止が義務づけられていない場所では、徐行し、安全を確認してから進行しましょう。
(2)見通しの良い交差点
見通しの良い交差点では、特に次の点を心がけましょう
①一時停止が義務づけられた場所では、確実な一時停止と安全確認を行いましょう
②優先道路を走行している場合を除き、一時停止が義務づけられていない場所でも、交差道路から車が接近している時は、徐行または一時停止をして交差道路側の車を先に行かせるようにしましょう