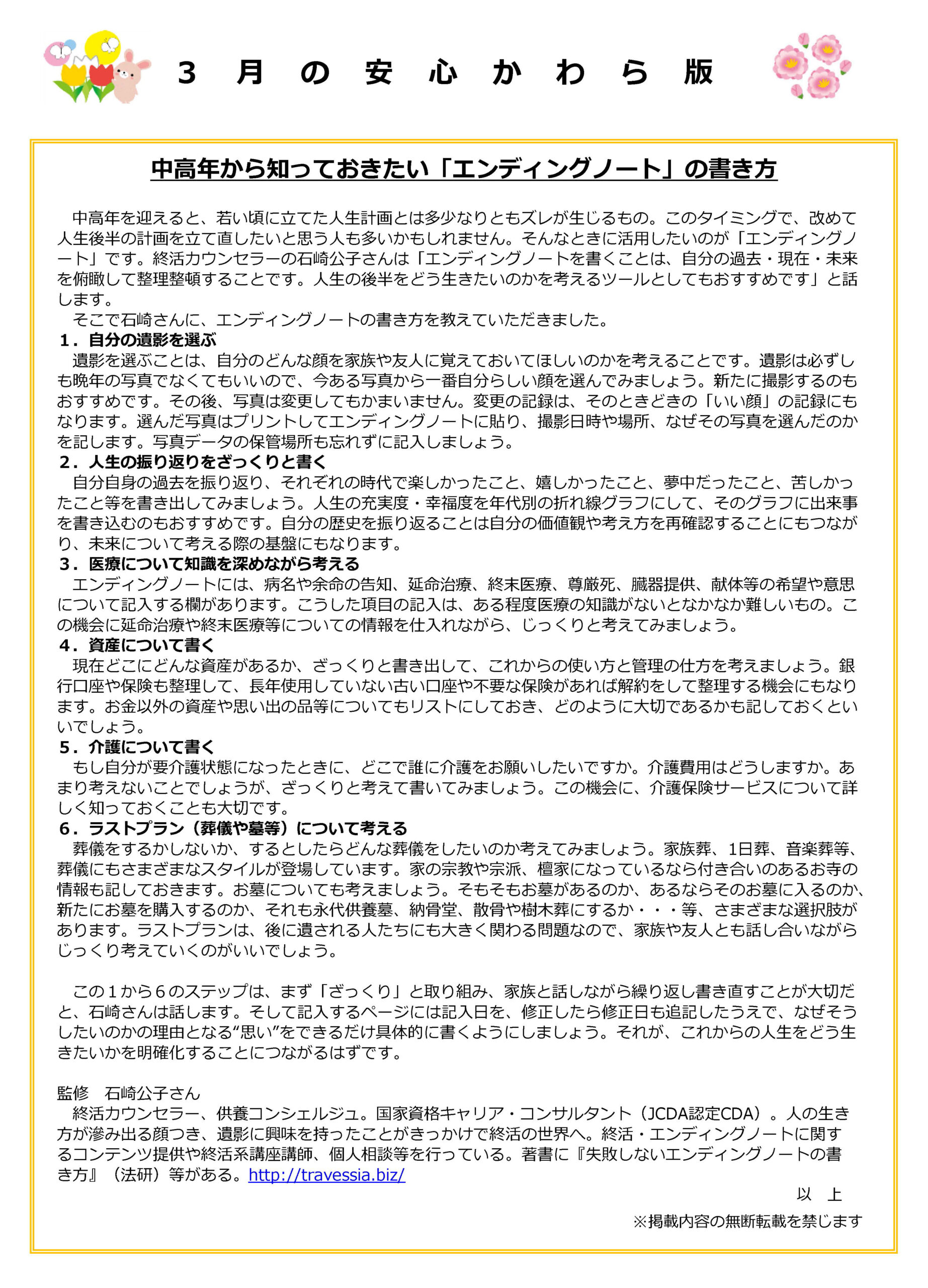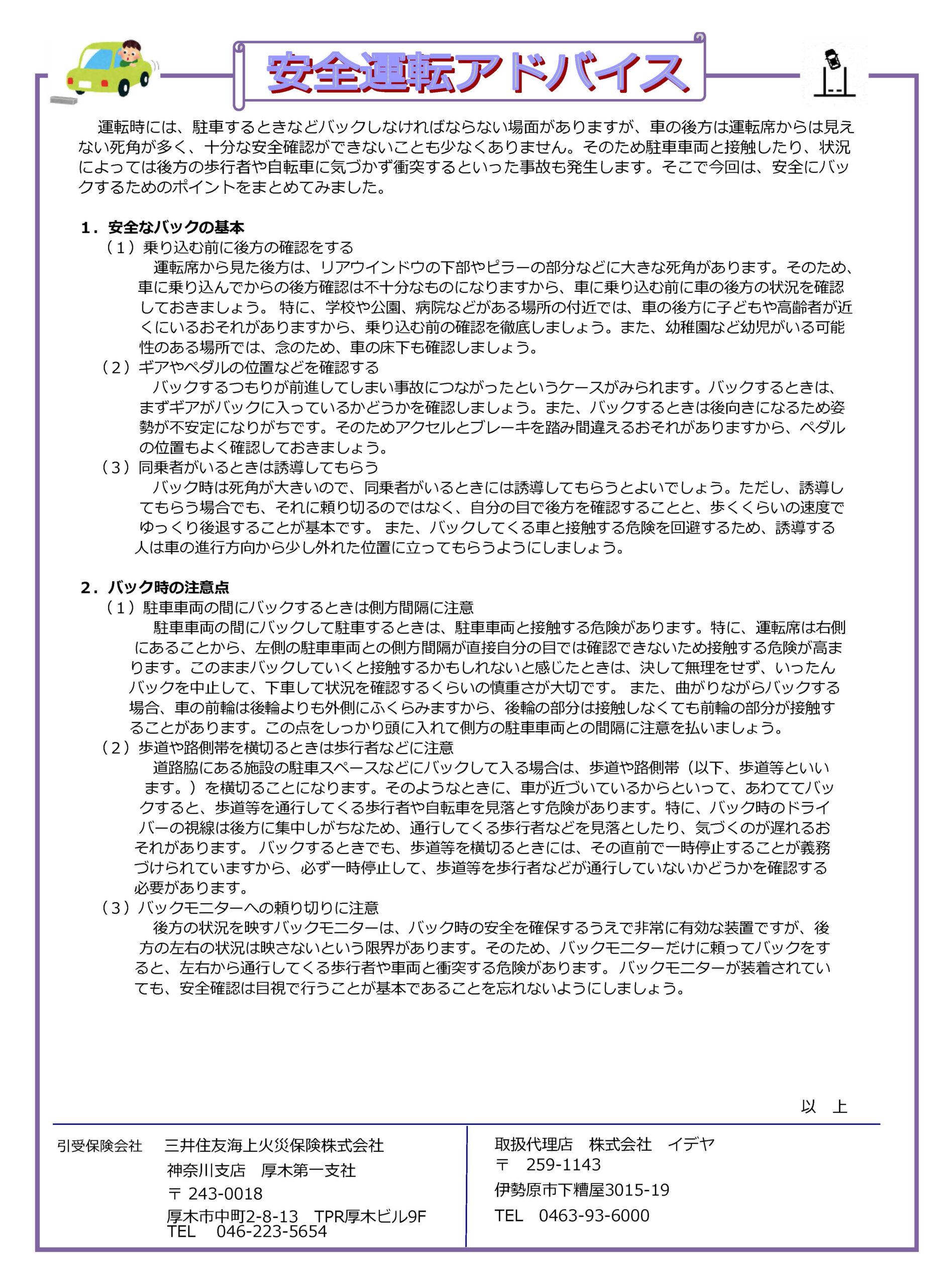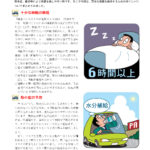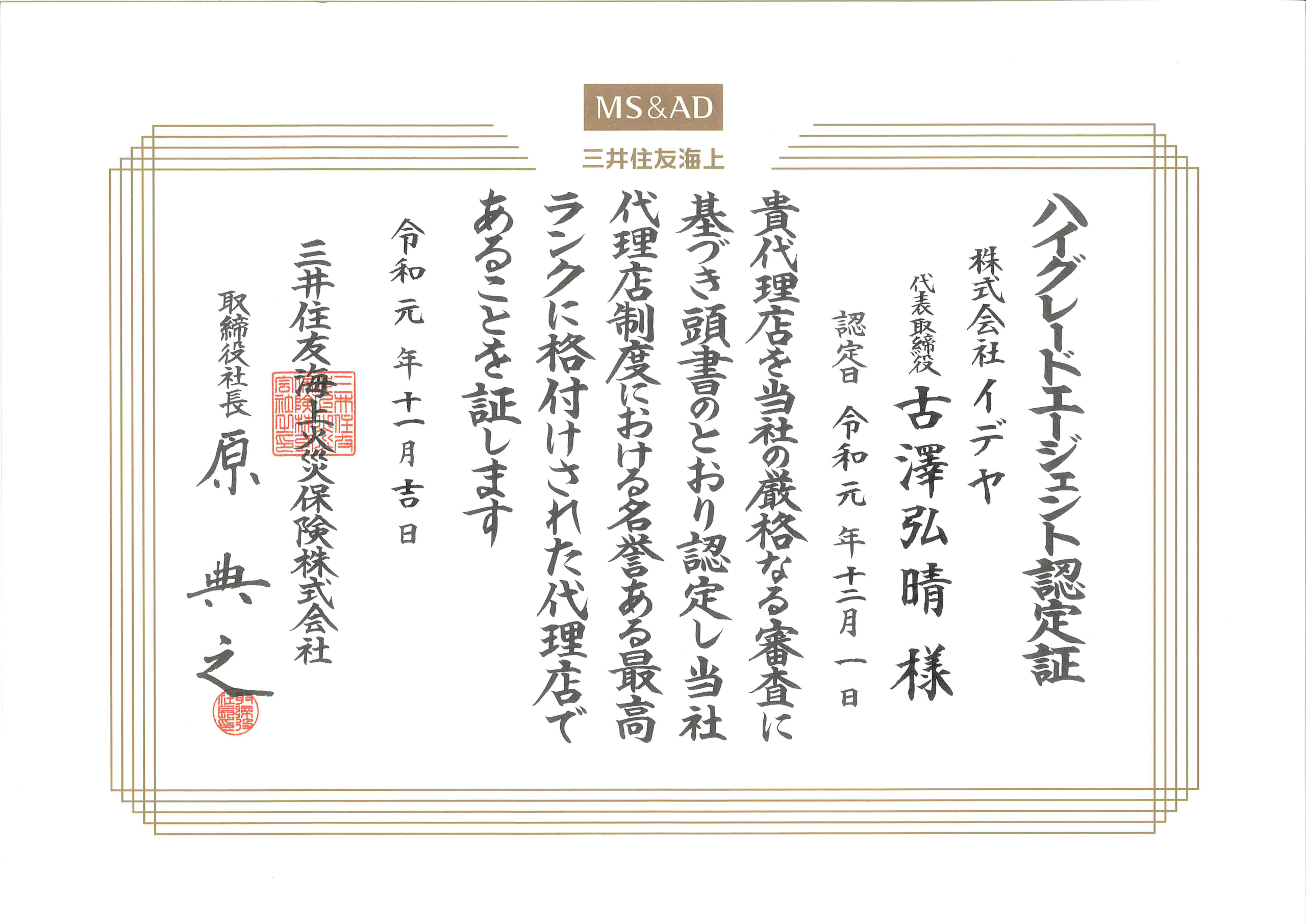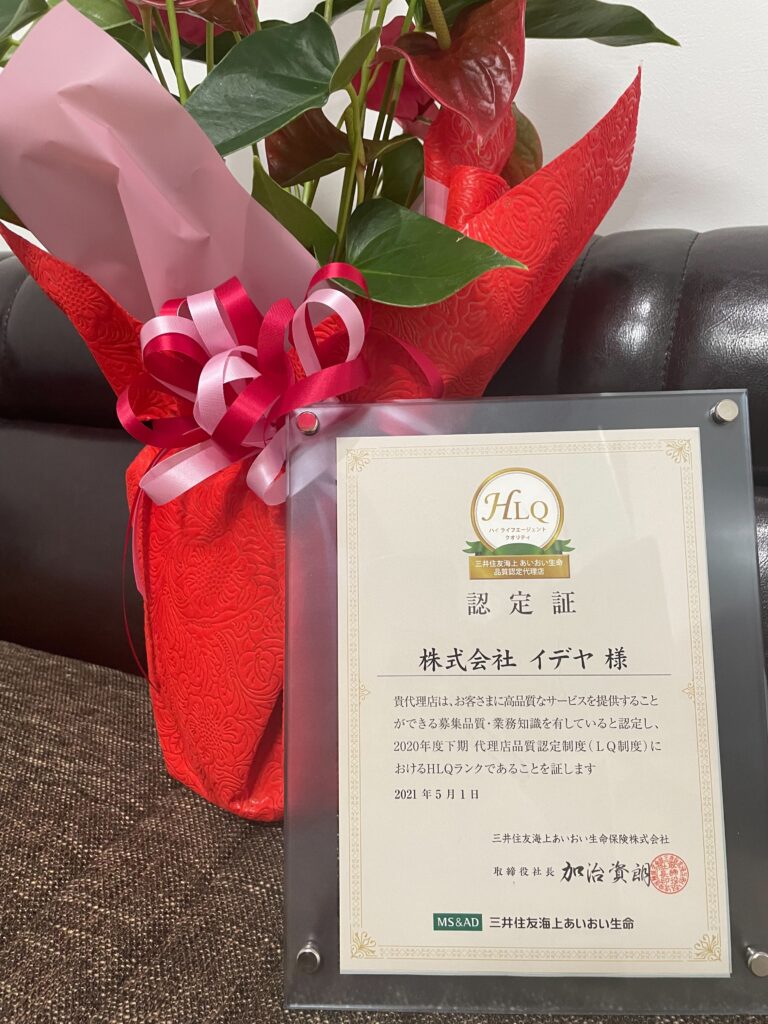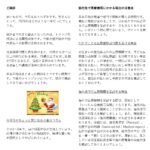3月の安心かわら版
中高年から知っておきたい「エンディングノート」の書き方
中高年を迎えると、若い頃に立てた人生計画とは多少なりともズレが生じるもの。このタイミングで、改めて人生後半の計画を立て直したいと思う人も多いかもしれません。そんなときに活用したいのが「エンディングノート」です。終活カウンセラーの石崎公子さんは「エンディングノートを書くことは、自分の過去・現在・未来を俯瞰して整理整頓することです。人生の後半をどう生きたいのかを考えるツールとしてもおすすめです」と話します。
そこで石崎さんに、エンディングノートの書き方を教えていただきました。
1.自分の遺影を選ぶ
遺影を選ぶことは、自分のどんな顔を家族や友人に覚えておいてほしいのかを考えることです。遺影は必ずしも晩年の写真でなくてもいいので、今ある写真から一番自分らしい顔を選んでみましょう。新たに撮影するのもおすすめです。その後、写真は変更してもかまいません。変更の記録は、そのときどきの「いい顔」の記録にもなります。選んだ写真はプリントしてエンディングノートに貼り、撮影日時や場所、なぜその写真を選んだのかを記します。写真データの保管場所も忘れずに記入しましょう。
2.人生の振り返りをざっくりと書く
自分自身の過去を振り返り、それぞれの時代で楽しかったこと、嬉しかったこと、夢中だったこと、苦しかったこと等を書き出してみましょう。人生の充実度・幸福度を年代別の折れ線グラフにして、そのグラフに出来事を書き込むのもおすすめです。自分の歴史を振り返ることは自分の価値観や考え方を再確認することにもつながり、未来について考える際の基盤にもなります。
3.医療について知識を深めながら考える
エンディングノートには、病名や余命の告知、延命治療、終末医療、尊厳死、臓器提供、献体等の希望や意思について記入する欄があります。こうした項目の記入は、ある程度医療の知識がないとなかなか難しいもの。この機会に延命治療や終末医療等についての情報を仕入れながら、じっくりと考えてみましょう。
4.資産について書く
現在どこにどんな資産があるか、ざっくりと書き出して、これからの使い方と管理の仕方を考えましょう。銀行口座や保険も整理して、長年使用していない古い口座や不要な保険があれば解約をして整理する機会にもなります。お金以外の資産や思い出の品等についてもリストにしておき、どのように大切であるかも記しておくといいでしょう。
5.介護について書く
もし自分が要介護状態になったときに、どこで誰に介護をお願いしたいですか。介護費用はどうしますか。あまり考えないことでしょうが、ざっくりと考えて書いてみましょう。この機会に、介護保険サービスについて詳しく知っておくことも大切です。
6.ラストプラン(葬儀や墓等)について考える
葬儀をするかしないか、するとしたらどんな葬儀をしたいのか考えてみましょう。家族葬、1日葬、音楽葬等、葬儀にもさまざまなスタイルが登場しています。家の宗教や宗派、檀家になっているなら付き合いのあるお寺の情報も記しておきます。お墓についても考えましょう。そもそもお墓があるのか、あるならそのお墓に入るのか、新たにお墓を購入するのか、それも永代供養墓、納骨堂、散骨や樹木葬にするか・・・等、さまざまな選択肢があります。ラストプランは、後に遺される人たちにも大きく関わる問題なので、家族や友人とも話し合いながらじっくり考えていくのがいいでしょう。
この1から6のステップは、まず「ざっくり」と取り組み、家族と話しながら繰り返し書き直すことが大切だと、石崎さんは話します。そして記入するページには記入日を、修正したら修正日も追記したうえで、なぜそうしたいのかの理由となる“思い”をできるだけ具体的に書くようにしましょう。それが、これからの人生をどう生きたいかを明確化することにつながるはずです。
監修 石崎公子さん
終活カウンセラー、供養コンシェルジュ。国家資格キャリア・コンサルタント(JCDA認定CDA)。人の生き方が滲み出る顔つき、遺影に興味を持ったことがきっかけで終活の世界へ。終活・エンディングノートに関するコンテンツ提供や終活系講座講師、個人相談等を行っている。著書に『失敗しないエンディングノートの書き方』(法研)等がある。http://travessia.biz/
安全運転アドバイス
運転時には、駐車するときなどバックしなければならない場面がありますが、車の後方は運転席からは見えない死角が多く、十分な安全確認ができないことも少なくありません。そのため駐車車両と接触したり、状況によっては後方の歩行者や自転車に気づかず衝突するといった事故も発生します。そこで今回は、安全にバックするためのポイントをまとめてみました。
1.安全なバックの基本
1)乗り込む前に後方の確認をする
運転席から見た後方は、リアウインドウの下部やピラーの部分などに大きな死角があります。そのため、車に乗り込んでからの後方確認は不十分なものになりますから、車に乗り込む前に車の後方の状況を確認しておきましょう。 特に、学校や公園、病院などがある場所の付近では、車の後方に子どもや高齢者が近くにいるおそれがありますから、乗り込む前の確認を徹底しましょう。また、幼稚園など幼児がいる可能性のある場所では、念のため、車の床下も確認しましょう。
2)ギアやペダルの位置などを確認する
バックするつもりが前進してしまい事故につながったというケースがみられます。バックするときは、まずギアがバックに入っているかどうかを確認しましょう。また、バックするときは後向きになるため姿勢が不安定になりがちです。そのためアクセルとブレーキを踏み間違えるおそれがありますから、ペダルの位置もよく確認しておきましょう。
3)同乗者がいるときは誘導してもらう
バック時は死角が大きいので、同乗者がいるときには誘導してもらうとよいでしょう。ただし、誘導してもらう場合でも、それに頼り切るのではなく、自分の目で後方を確認することと、歩くくらいの速度でゆっくり後退することが基本です。 また、バックしてくる車と接触する危険を回避するため、誘導する人は車の進行方向から少し外れた位置に立ってもらうようにしましょう。
2.バック時の注意点
1)駐車車両の間にバックするときは側方間隔に注意
駐車車両の間にバックして駐車するときは、駐車車両と接触する危険があります。特に、運転席は右側にあることから、左側の駐車車両との側方間隔が直接自分の目では確認できないため接触する危険が高まります。このままバックしていくと接触するかもしれないと感じたときは、決して無理をせず、いったんバックを中止して、下車して状況を確認するくらいの慎重さが大切です。 また、曲がりながらバックする場合、車の前輪は後輪よりも外側にふくらみますから、後輪の部分は接触しなくても前輪の部分が接触することがあります。この点をしっかり頭に入れて側方の駐車車両との間隔に注意を払いましょう。
2)歩道や路側帯を横切るときは歩行者などに注意
道路脇にある施設の駐車スペースなどにバックして入る場合は、歩道や路側帯(以下、歩道等といいます。)を横切ることになります。そのようなときに、車が近づいているからといって、あわててバックすると、歩道等を通行してくる歩行者や自転車を見落とす危険があります。特に、バック時のドライバーの視線は後方に集中しがちなため、通行してくる歩行者などを見落としたり、気づくのが遅れるおそれがあります。 バックするときでも、歩道等を横切るときには、その直前で一時停止することが義務づけられていますから、必ず一時停止して、歩道等を歩行者などが通行していないかどうかを確認する必要があります。
3)バックモニターへの頼り切りに注意
後方の状況を映すバックモニターは、バック時の安全を確保するうえで非常に有効な装置ですが、後方の左右の状況は映さないという限界があります。そのため、バックモニターだけに頼ってバックをすると、左右から通行してくる歩行者や車両と衝突する危険があります。 バックモニターが装着されていても、安全確認は目視で行うことが基本であることを忘れないようにしましょう。