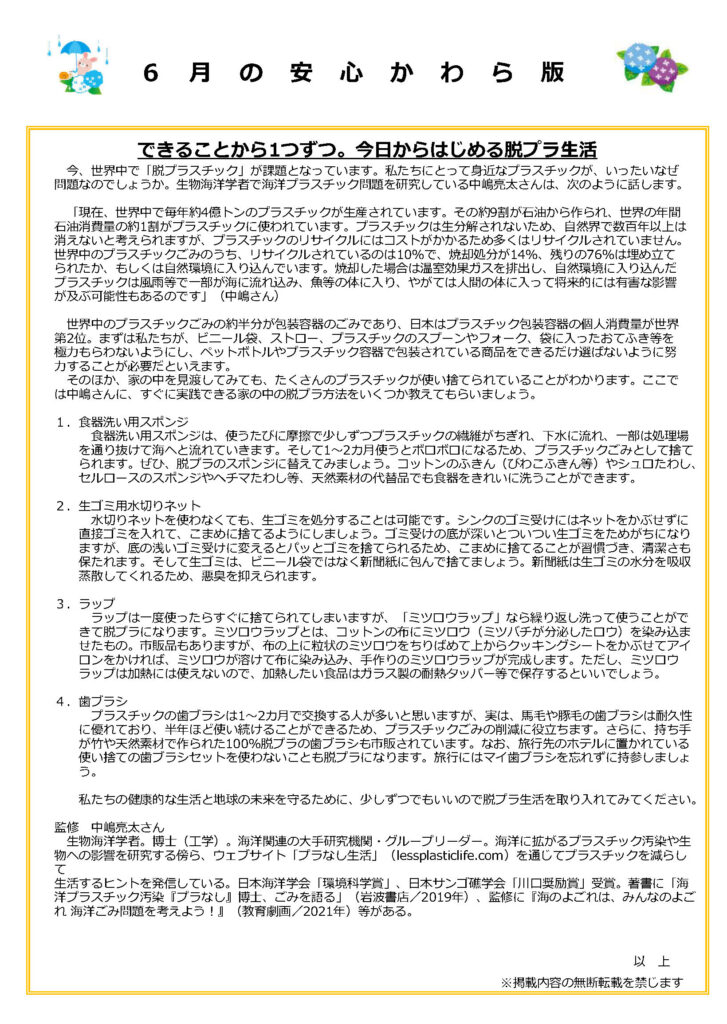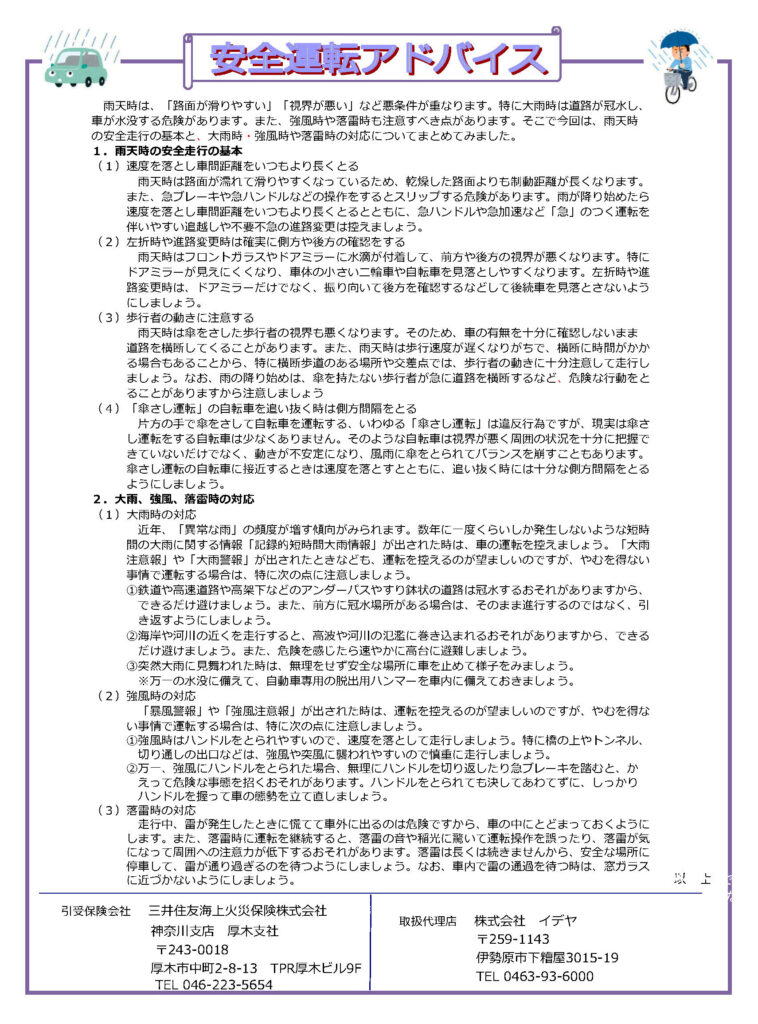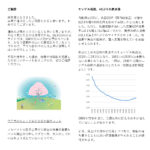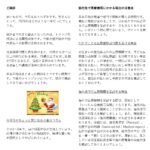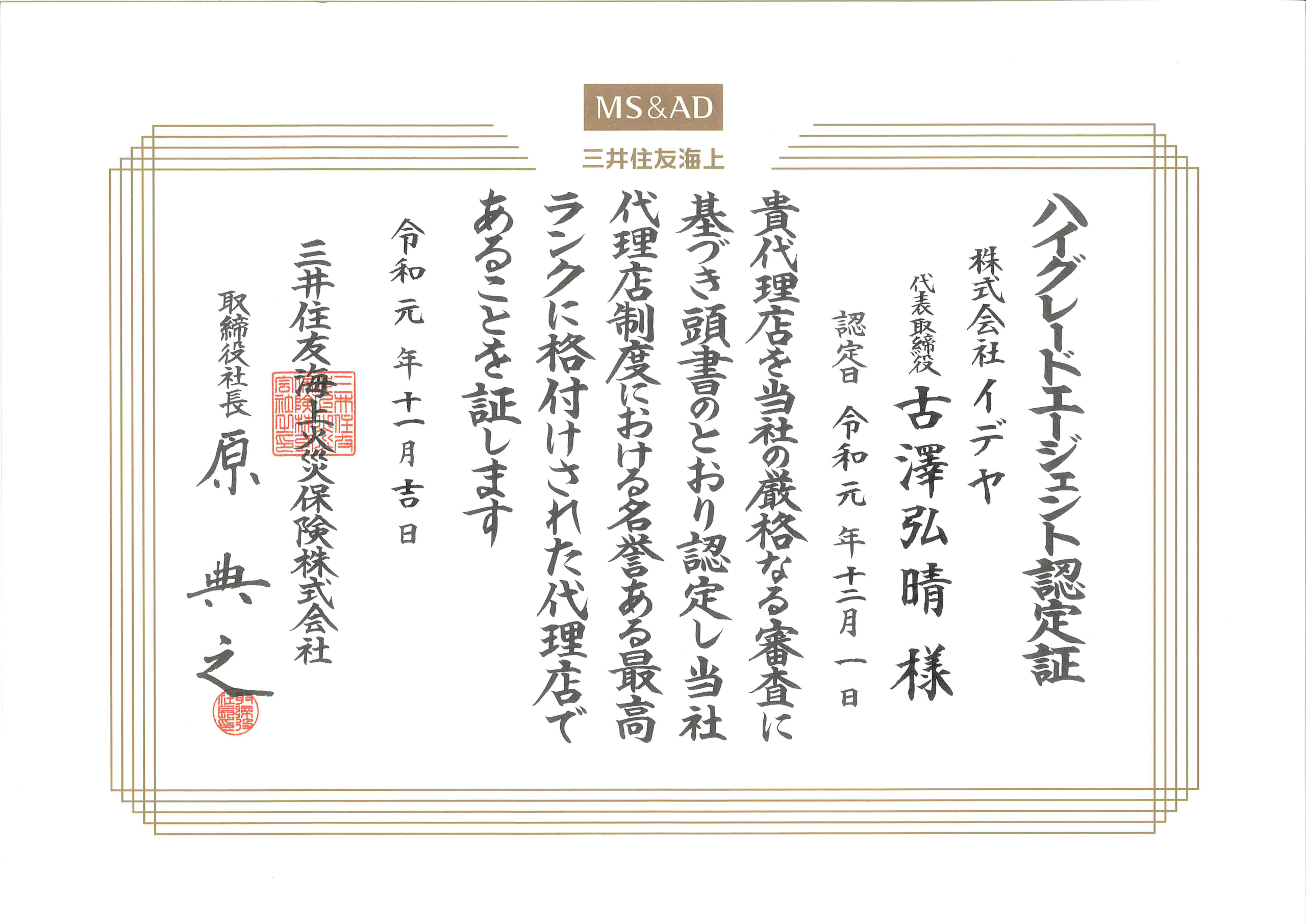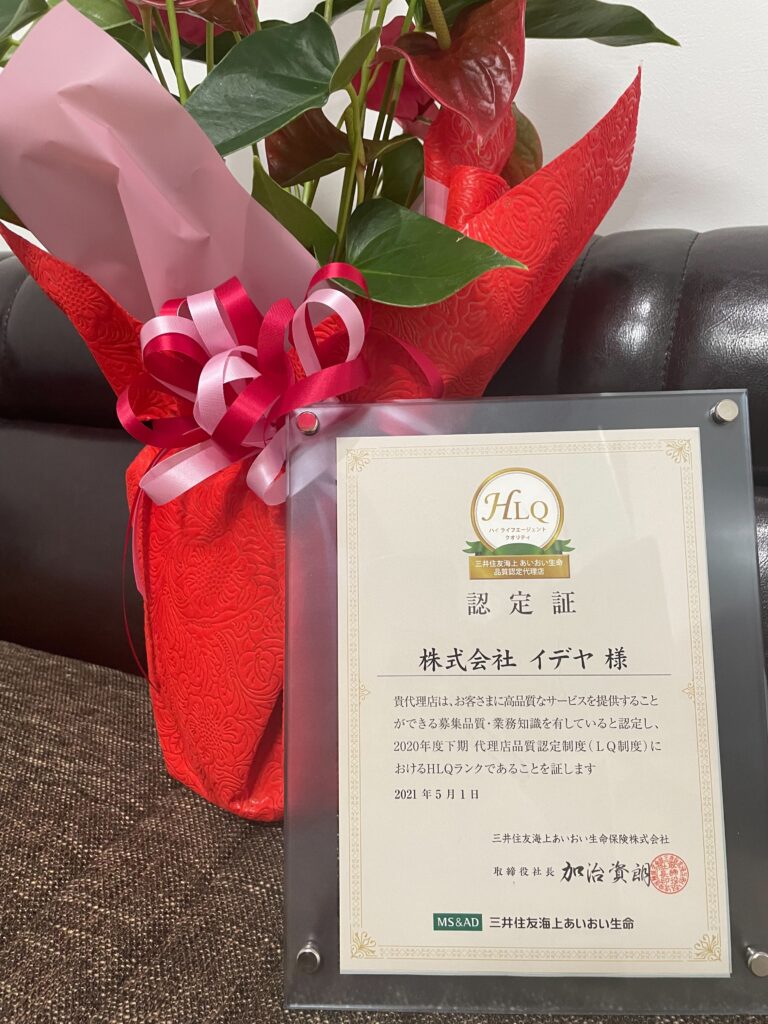2022年6月の安心かわら版
できることから1つずつ。今日からはじめる脱プラ生活
今、世界中で「脱プラスチック」が課題となっています。私たちにとって身近なプラスチックが、いったいなぜ問題なのでしょうか。生物海洋学者で海洋プラスチック問題を研究している中嶋亮太さんは、次のように話します。
「現在、世界中で毎年約4億トンのプラスチックが生産されています。その約9割が石油から作られ、世界の年間石油消費量の約1割がプラスチックに使われています。プラスチックは生分解されないため、自然界で数百年以上は消えないと考えられますが、プラスチックのリサイクルにはコストがかかるため多くはリサイクルされていません。世界中のプラスチックごみのうち、リサイクルされているのは10%で、焼却処分が14%、残りの76%は埋め立てられたか、もしくは自然環境に入り込んでいます。焼却した場合は温室効果ガスを排出し、自然環境に入り込んだプラスチックは風雨等で一部が海に流れ込み、魚等の体に入り、やがては人間の体に入って将来的には有害な影響が及ぶ可能性もあるのです」(中嶋さん)
世界中のプラスチックごみの約半分が包装容器のごみであり、日本はプラスチック包装容器の個人消費量が世界第2位。まずは私たちが、ビニール袋、ストロー、プラスチックのスプーンやフォーク、袋に入ったおてふき等を極力もらわないようにし、ペットボトルやプラスチック容器で包装されている商品をできるだけ選ばないように努力することが必要だといえます。
そのほか、家の中を見渡してみても、たくさんのプラスチックが使い捨てられていることがわかります。ここでは中嶋さんに、すぐに実践できる家の中の脱プラ方法をいくつか教えてもらいましょう。
食器洗い用スポンジ
食器洗い用スポンジは、使うたびに摩擦で少しずつプラスチックの繊維がちぎれ、下水に流れ、一部は処理場を通り抜けて海へと流れていきます。そして1~2カ月使うとボロボロになるため、プラスチックごみとして捨てられます。ぜひ、脱プラのスポンジに替えてみましょう。コットンのふきん(びわこふきん等)やシュロたわし、セルロースのスポンジやヘチマたわし等、天然素材の代替品でも食器をきれいに洗うことができます。
生ゴミ用水切りネット
水切りネットを使わなくても、生ゴミを処分することは可能です。シンクのゴミ受けにはネットをかぶせずに直接ゴミを入れて、こまめに捨てるようにしましょう。ゴミ受けの底が深いとついつい生ゴミをためがちになりますが、底の浅いゴミ受けに変えるとパッとゴミを捨てられるため、こまめに捨てることが習慣づき、清潔さも保たれます。そして生ゴミは、ビニール袋ではなく新聞紙に包んで捨てましょう。新聞紙は生ゴミの水分を吸収蒸散してくれるため、悪臭を抑えられます。
ラップ
ラップは一度使ったらすぐに捨てられてしまいますが、「ミツロウラップ」なら繰り返し洗って使うことができて脱プラになります。ミツロウラップとは、コットンの布にミツロウ(ミツバチが分泌したロウ)を染み込ませたもの。市販品もありますが、布の上に粒状のミツロウをちりばめて上からクッキングシートをかぶせてアイロンをかければ、ミツロウが溶けて布に染み込み、手作りのミツロウラップが完成します。ただし、ミツロウラップは加熱には使えないので、加熱したい食品はガラス製の耐熱タッパー等で保存するといいでしょう。
歯ブラシ
プラスチックの歯ブラシは1~2カ月で交換する人が多いと思いますが、実は、馬毛や豚毛の歯ブラシは耐久性に優れており、半年ほど使い続けることができるため、プラスチックごみの削減に役立ちます。さらに、持ち手が竹や天然素材で作られた100%脱プラの歯ブラシも市販されています。なお、旅行先のホテルに置かれている使い捨ての歯ブラシセットを使わないことも脱プラになります。旅行にはマイ歯ブラシを忘れずに持参しましょう。
私たちの健康的な生活と地球の未来を守るために、少しずつでもいいので脱プラ生活を取り入れてみてください。
監修 中嶋亮太さん
生物海洋学者。博士(工学)。海洋関連の大手研究機関・グループリーダー。海洋に拡がるプラスチック汚染や生物への影響を研究する傍ら、ウェブサイト「プラなし生活」(lessplasticlife.com)を通じてプラスチックを減らして生活するヒントを発信している。日本海洋学会「環境科学賞」、日本サンゴ礁学会「川口奨励賞」受賞。著書に「海洋プラスチック汚染『プラなし』博士、ごみを語る」(岩波書店/2019年)、監修に『海のよごれは、みんなのよごれ海洋ごみ問題を考えよう!』(教育劇画/2021年)等がある。
安全運転アドバイス
雨天時は、「路面が滑りやすい」「視界が悪い」など悪条件が重なります。特に大雨時は道路が冠水し、車が水没する危険があります。また、強風時や落雷時も注意すべき点があります。そこで今回は、雨天時の安全走行の基本と、大雨時・強風時や落雷時の対応についてまとめてみました。
雨天時の安全走行の基本
(1)速度を落とし車間距離をいつもより長くとる
雨天時は路面が濡れて滑りやすくなっているため、乾燥した路面よりも制動距離が長くなります。また、急ブレーキや急ハンドルなどの操作をするとスリップする危険があります。雨が降り始めたら速度を落とし車間距離をいつもより長くとるとともに、急ハンドルや急加速など「急」のつく運転を伴いやすい追越しや不要不急の進路変更は控えましょう。
(2)左折時や進路変更時は確実に側方や後方の確認をする
雨天時はフロントガラスやドアミラーに水滴が付着して、前方や後方の視界が悪くなります。特にドアミラーが見えにくくなり、車体の小さい二輪車や自転車を見落としやすくなります。左折時や進路変更時は、ドアミラーだけでなく、振り向いて後方を確認するなどして後続車を見落とさないようにしましょう。
(3)歩行者の動きに注意する
雨天時は傘をさした歩行者の視界も悪くなります。そのため、車の有無を十分に確認しないまま道路を横断してくることがあります。また、雨天時は歩行速度が遅くなりがちで、横断に時間がかかる場合もあることから、特に横断歩道のある場所や交差点では、歩行者の動きに十分注意して走行しましょう。なお、雨の降り始めは、傘を持たない歩行者が急に道路を横断するなど、危険な行動をとることがありますから注意しましょう
(4)「傘さし運転」の自転車を追い抜く時は側方間隔をとる
片方の手で傘をさして自転車を運転する、いわゆる「傘さし運転」は違反行為ですが、現実は傘さし運転をする自転車は少なくありません。そのような自転車は視界が悪く周囲の状況を十分に把握できていないだけでなく、動きが不安定になり、風雨に傘をとられてバランスを崩すこともあります。傘さし運転の自転車に接近するときは速度を落とすとともに、追い抜く時には十分な側方間隔をとるようにしましょう。
大雨、強風、落雷時の対応
(1)大雨時の対応
近年、「異常な雨」の頻度が増す傾向がみられます。数年に一度くらいしか発生しないような短時間の大雨に関する情報「記録的短時間大雨情報」が出された時は、車の運転を控えましょう。「大雨注意報」や「大雨警報」が出されたときなども、運転を控えるのが望ましいのですが、やむを得ない事情で運転する場合は、特に次の点に注意しましょう。
①鉄道や高速道路や高架下などのアンダーパスやすり鉢状の道路は冠水するおそれがありますから、できるだけ避けましょう。また、前方に冠水場所がある場合は、そのまま進行するのではなく、引き返すようにしましょう。
②海岸や河川の近くを走行すると、高波や河川の氾濫に巻き込まれるおそれがありますから、できるだけ避けましょう。また、危険を感じたら速やかに高台に避難しましょう。
③突然大雨に見舞われた時は、無理をせず安全な場所に車を止めて様子をみましょう。※万一の水没に備えて、自動車専用の脱出用ハンマーを車内に備えておきましょう。
(2)強風時の対応
「暴風警報」や「強風注意報」が出された時は、運転を控えるのが望ましいのですが、やむを得ない事情で運転する場合は、特に次の点に注意しましょう。
①強風時はハンドルをとられやすいので、速度を落として走行しましょう。特に橋の上やトンネル、切り通しの出口などは、強風や突風に襲われやすいので慎重に走行しましょう。
②万一、強風にハンドルをとられた場合、無理にハンドルを切り返したり急ブレーキを踏むと、かえって危険な事態を招くおそれがあります。ハンドルをとられても決してあわてずに、しっかりハンドルを握って車の態勢を立て直しましょう。
(3)落雷時の対応
走行中、雷が発生したときに慌てて車外に出るのは危険ですから、車の中にとどまっておくようにします。また、落雷時に運転を継続すると、落雷の音や稲光に驚いて運転操作を誤ったり、落雷が気になって周囲への注意力が低下するおそれがあります。落雷は長くは続きませんから、安全な場所に停車して、雷が通り過ぎるのを待つようにしましょう。なお、車内で雷の通過を待つ時は、窓ガラスに近づかないようにしましょう。