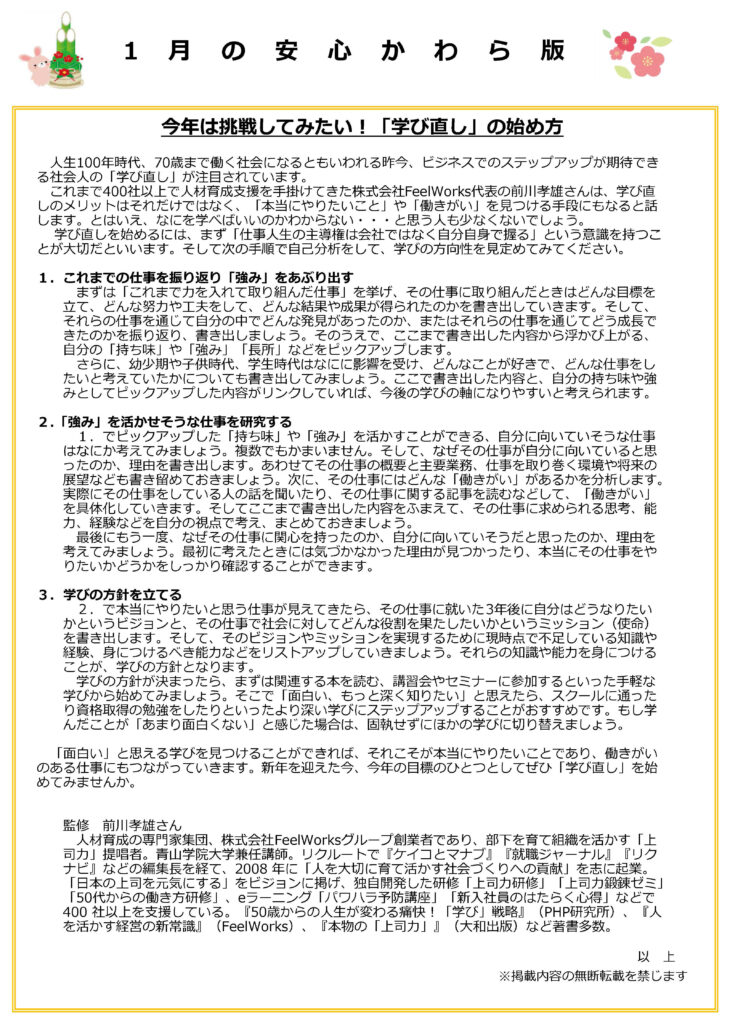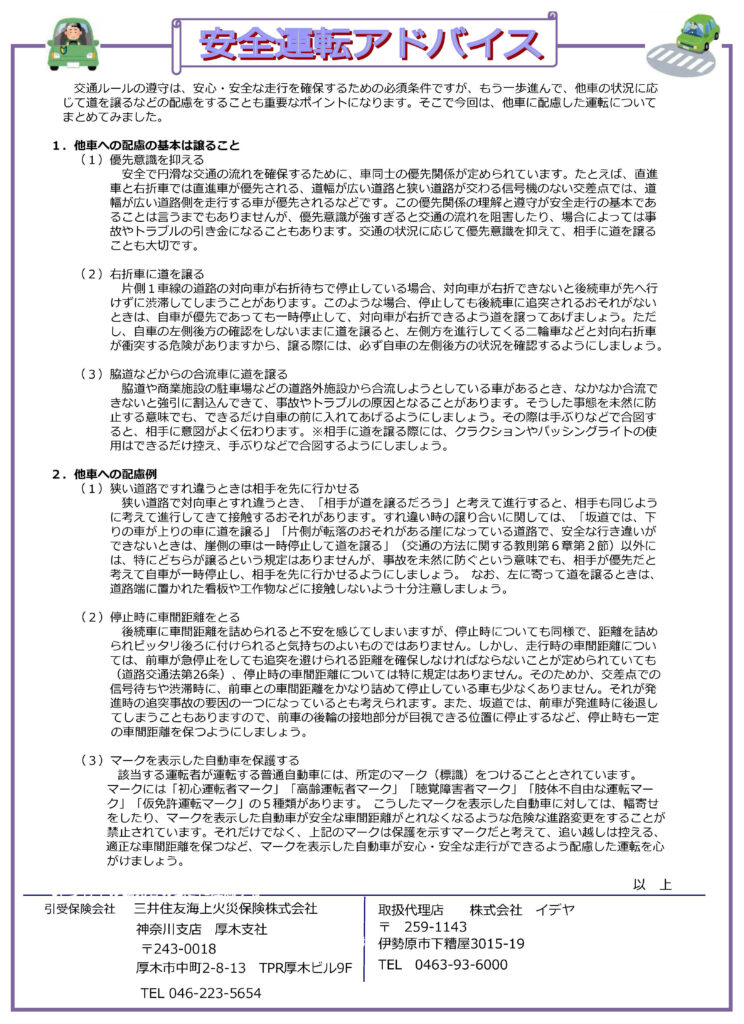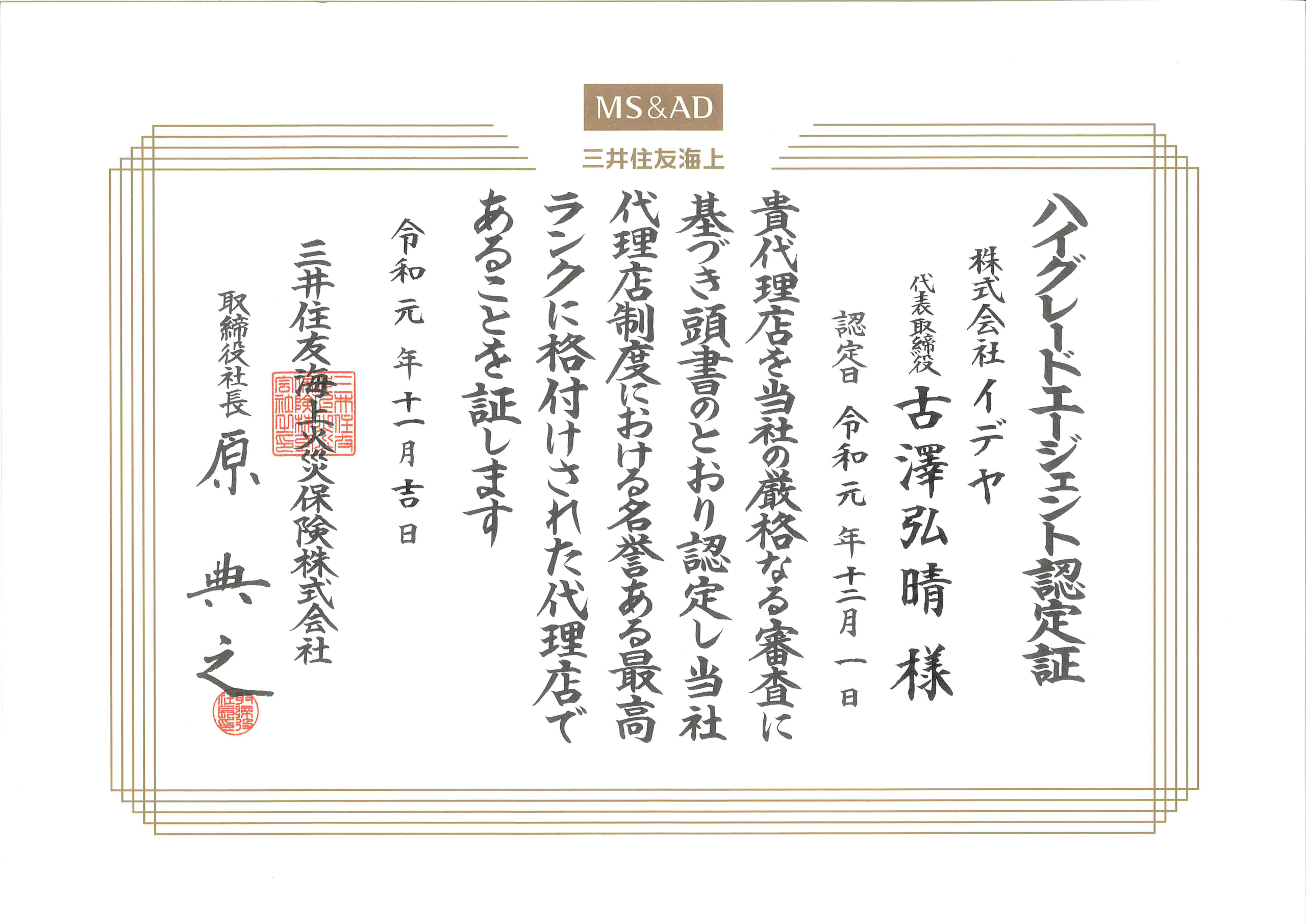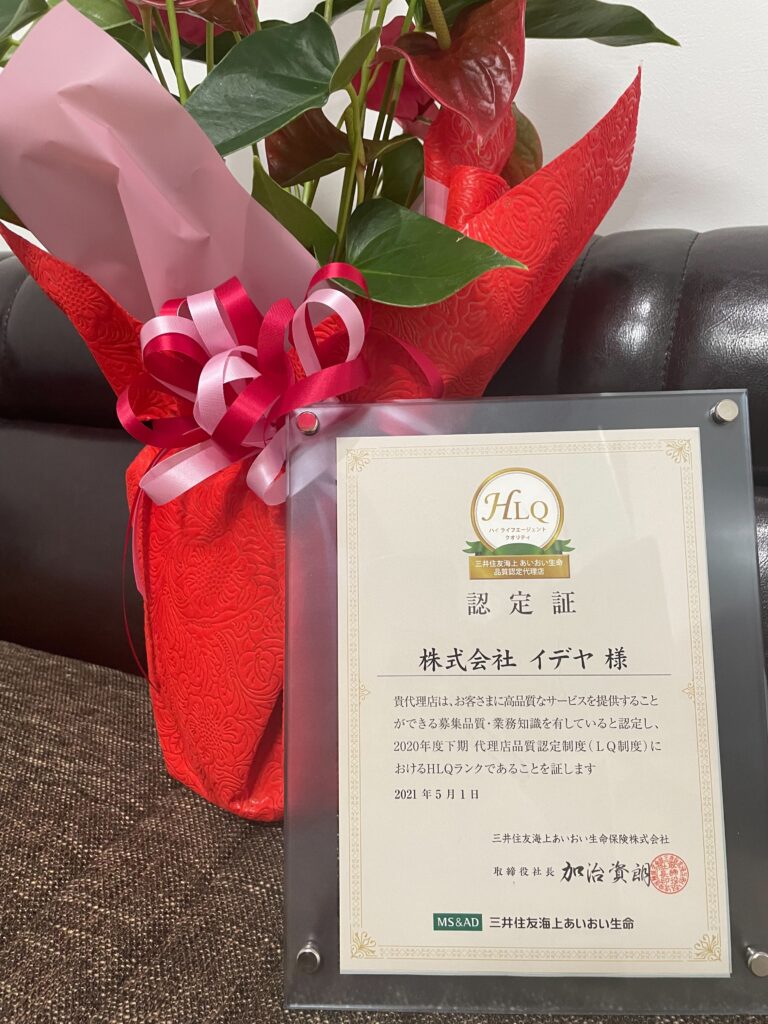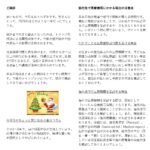2022年1月の安心かわら版
今年は挑戦してみたい!「学び直し」の始め方
人生100年時代、70歳まで働く社会になるともいわれる昨今、ビジネスでのステップアップが期待できる社会人の「学び直し」が注目されています。
これまで400社以上で人材育成支援を手掛けてきた株式会社FeelWorks代表の前川孝雄さんは、学び直しのメリットはそれだけではなく、「本当にやりたいこと」や「働きがい」を見つける手段にもなると話します。とはいえ、なにを学べばいいのかわからない・・・と思う人も少なくないでしょう。
学び直しを始めるには、まず「仕事人生の主導権は会社ではなく自分自身で握る」という意識を持つことが大切だといいます。そして次の手順で自己分析をして、学びの方向性を見定めてみてください。
これまでの仕事を振り返り「強み」をあぶり出す
まずは「これまで力を入れて取り組んだ仕事」を挙げ、その仕事に取り組んだときはどんな目標を立て、どんな努力や工夫をして、どんな結果や成果が得られたのかを書き出していきます。そして、それらの仕事を通じて自分の中でどんな発見があったのか、またはそれらの仕事を通じてどう成長できたのかを振り返り、書き出しましょう。そのうえで、ここまで書き出した内容から浮かび上がる、自分の「持ち味」や「強み」「長所」などをピックアップします。さらに、幼少期や子供時代、学生時代はなにに影響を受け、どんなことが好きで、どんな仕事をしたいと考えていたかについても書き出してみましょう。ここで書き出した内容と、自分の持ち味や強みとしてピックアップした内容がリンクしていれば、今後の学びの軸になりやすいと考えられます。
「強み」を活かせそうな仕事を研究する
1.でピックアップした「持ち味」や「強み」を活かすことができる、自分に向いていそうな仕事はなにか考えてみましょう。複数でもかまいません。そして、なぜその仕事が自分に向いていると思ったのか、理由を書き出します。あわせてその仕事の概要と主要業務、仕事を取り巻く環境や将来の展望なども書き留めておきましょう。次に、その仕事にはどんな「働きがい」があるかを分析します。実際にその仕事をしている人の話を聞いたり、その仕事に関する記事を読むなどして、「働きがい」を具体化していきます。そしてここまで書き出した内容をふまえて、その仕事に求められる思考、能力、経験などを自分の視点で考え、まとめておきましょう。最後にもう一度、なぜその仕事に関心を持ったのか、自分に向いていそうだと思ったのか、理由を考えてみましょう。最初に考えたときには気づかなかった理由が見つかったり、本当にその仕事をやりたいかどうかをしっかり確認することができます。
学びの方針を立てる
2.で本当にやりたいと思う仕事が見えてきたら、その仕事に就いた3年後に自分はどうなりたいかというビジョンと、その仕事で社会に対してどんな役割を果たしたいかというミッション(使命)を書き出します。そして、そのビジョンやミッションを実現するために現時点で不足している知識や経験、身につけるべき能力などをリストアップしていきましょう。それらの知識や能力を身につけることが、学びの方針となります。学びの方針が決まったら、まずは関連する本を読む、講習会やセミナーに参加するといった手軽な学びから始めてみましょう。そこで「面白い、もっと深く知りたい」と思えたら、スクールに通ったり資格取得の勉強をしたりといったより深い学びにステップアップすることがおすすめです。もし学んだことが「あまり面白くない」と感じた場合は、固執せずにほかの学びに切り替えましょう。
「面白い」と思える学びを見つけることができれば、それこそが本当にやりたいことであり、働きがいのある仕事にもつながっていきます。新年を迎えた今、今年の目標のひとつとしてぜひ「学び直し」を始めてみませんか。
監修 前川孝雄さん
人材育成の専門家集団、株式会社FeelWorksグループ創業者であり、部下を育て組織を活かす「上司力」提唱者。青山学院大学兼任講師。リクルートで『ケイコとマナブ』『就職ジャーナル』『リクナビ』などの編集長を経て、2008年に「人を大切に育て活かす社会づくりへの貢献」を志に起業。「日本の上司を元気にする」をビジョンに掲げ、独自開発した研修「上司力研修」「上司力鍛錬ゼミ」「50代からの働き方研修」、eラーニング「パワハラ予防講座」「新入社員のはたらく心得」などで400社以上を支援している。『50歳からの人生が変わる痛快!「学び」戦略』(PHP研究所)、『人を活かす経営の新常識』(FeelWorks)、『本物の「上司力」』(大和出版)など著書多数。株式会社FeelWorks
https://www.feelworks.jp/
安全運転アドバイス
交通ルールの遵守は、安心・安全な走行を確保するための必須条件ですが、もう一歩進んで、他車の状況に応じて道を譲るなどの配慮をすることも重要なポイントになります。そこで今回は、他車に配慮した運転についてまとめてみました。
他車への配慮の基本は譲ること
(1)優先意識を抑える
安全で円滑な交通の流れを確保するために、車同士の優先関係が定められています。たとえば、直進車と右折車では直進車が優先される、道幅が広い道路と狭い道路が交わる信号機のない交差点では、道幅が広い道路側を走行する車が優先されるなどです。この優先関係の理解と遵守が安全走行の基本であることは言うまでもありませんが、優先意識が強すぎると交通の流れを阻害したり、場合によっては事故やトラブルの引き金になることもあります。交通の状況に応じて優先意識を抑えて、相手に道を譲ることも大切です。
(2)右折車に道を譲る
片側1車線の道路の対向車が右折待ちで停止している場合、対向車が右折できないと後続車が先へ行けずに渋滞してしまうことがあります。このような場合、停止しても後続車に追突されるおそれがないときは、自車が優先であっても一時停止して、対向車が右折できるよう道を譲ってあげましょう。ただし、自車の左側後方の確認をしないままに道を譲ると、左側方を進行してくる二輪車などと対向右折車が衝突する危険がありますから、譲る際には、必ず自車の左側後方の状況を確認するようにしましょう。
(3)脇道などからの合流車に道を譲る
脇道や商業施設の駐車場などの道路外施設から合流しようとしている車があるとき、なかなか合流できないと強引に割込んできて、事故やトラブルの原因となることがあります。そうした事態を未然に防止する意味でも、できるだけ自車の前に入れてあげるようにしましょう。その際は手ぶりなどで合図すると、相手に意図がよく伝わります。※相手に道を譲る際には、クラクションやパッシングライトの使用はできるだけ控え、手ぶりなどで合図するようにしましょう。
他車への配慮例
(1)狭い道路ですれ違うときは相手を先に行かせる
狭い道路で対向車とすれ違うとき、「相手が道を譲るだろう」と考えて進行すると、相手も同じように考えて進行してきて接触するおそれがあります。すれ違い時の譲り合いに関しては、「坂道では、下りの車が上りの車に道を譲る」「片側が転落のおそれがある崖になっている道路で、安全な行き違いができないときは、崖側の車は一時停止して道を譲る」(交通の方法に関する教則第6章第2節)以外には、特にどちらが譲るという規定はありませんが、事故を未然に防ぐという意味でも、相手が優先だと考えて自車が一時停止し、相手を先に行かせるようにしましょう。なお、左に寄って道を譲るときは、道路端に置かれた看板や工作物などに接触しないよう十分注意しましょう。
(2)停止時に車間距離をとる
後続車に車間距離を詰められると不安を感じてしまいますが、停止時についても同様で、距離を詰められピッタリ後ろに付けられると気持ちのよいものではありません。しかし、走行時の車間距離については、前車が急停止をしても追突を避けられる距離を確保しなければならないことが定められていても(道路交通法第26条)、停止時の車間距離については特に規定はありません。そのためか、交差点での信号待ちや渋滞時に、前車との車間距離をかなり詰めて停止している車も少なくありません。それが発進時の追突事故の要因の一つになっているとも考えられます。また、坂道では、前車が発進時に後退してしまうこともありますので、前車の後輪の接地部分が目視できる位置に停止するなど、停止時も一定の車間距離を保つようにしましょう。
(3)マークを表示した自動車を保護する
該当する運転者が運転する普通自動車には、所定のマーク(標識)をつけることとされています。マークには「初心運転者マーク」「高齢運転者マーク」「聴覚障害者マーク」「肢体不自由な運転マーク」「仮免許運転マーク」の5種類があります。こうしたマークを表示した自動車に対しては、幅寄せをしたり、マークを表示した自動車が安全な車間距離がとれなくなるような危険な進路変更をすることが禁止されています。それだけでなく、上記のマークは保護を示すマークだと考えて、追い越しは控える、適正な車間距離を保つなど、マークを表示した自動車が安心・安全な走行ができるよう配慮した運転を心がけましょう。