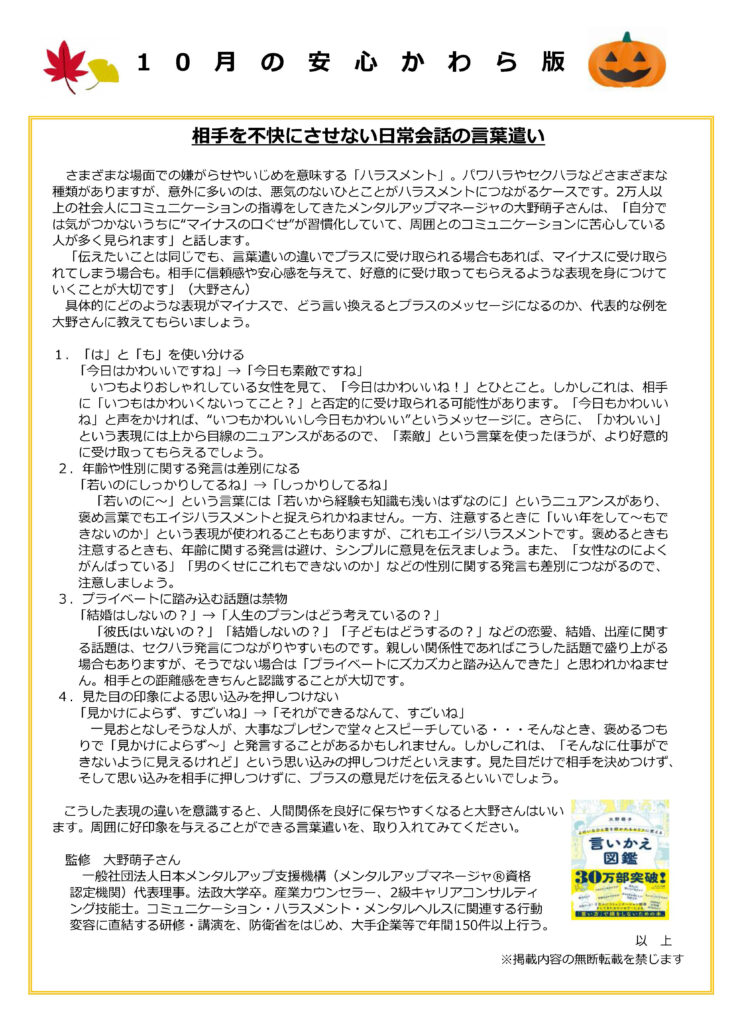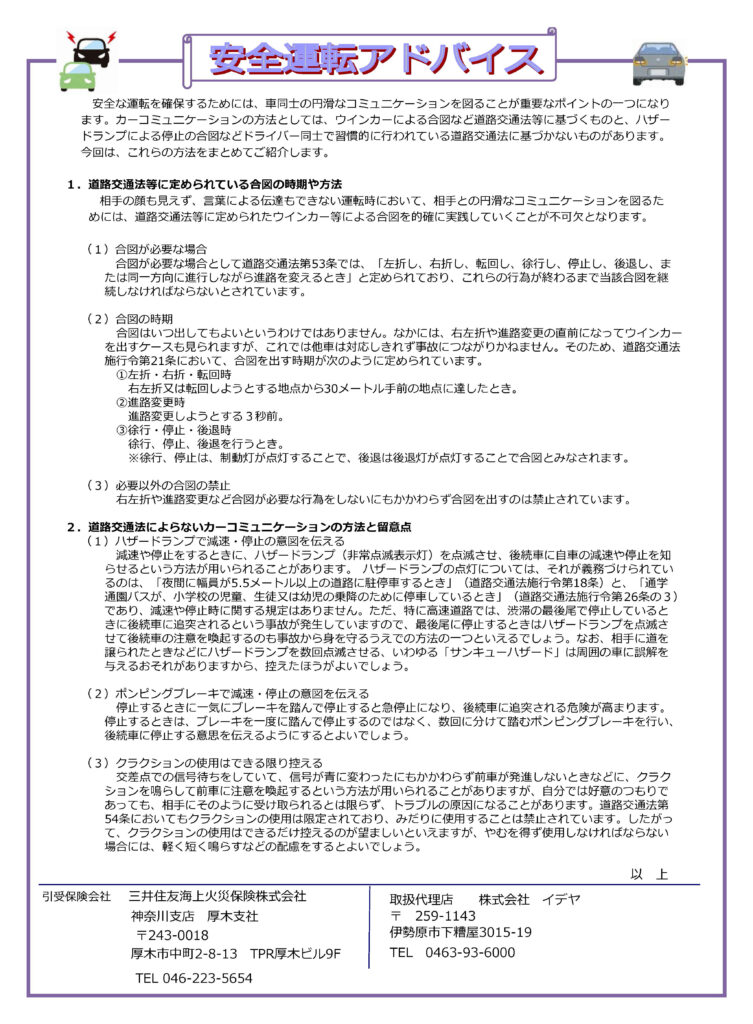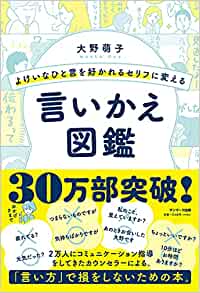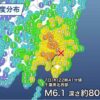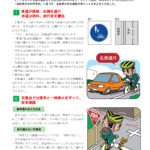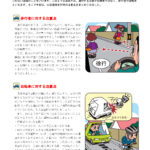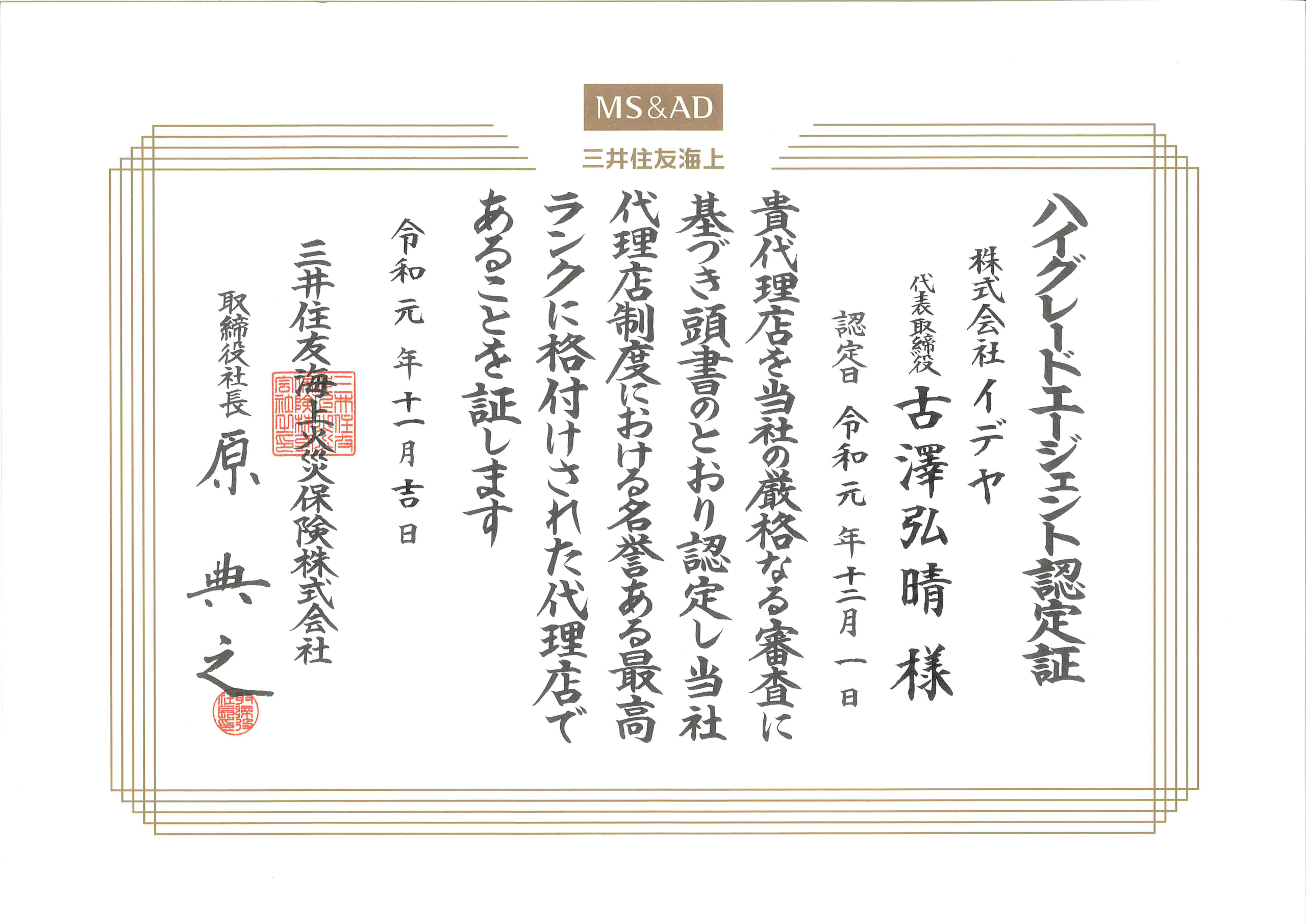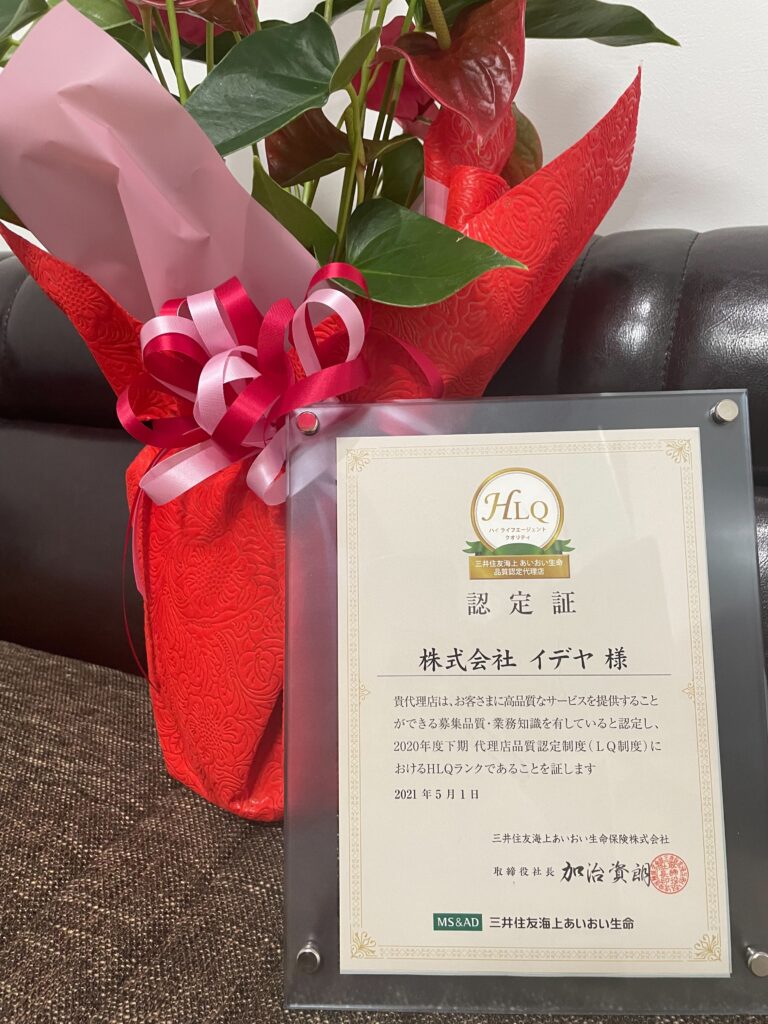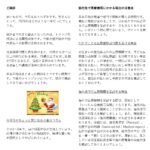10月の安心かわら版
相手を不快にさせない日常会話の言葉遣い
さまざまな場面での嫌がらせやいじめを意味する「ハラスメント」。パワハラやセクハラなどさまざまな種類がありますが、意外に多いのは、悪気のないひとことがハラスメントにつながるケースです。2万人以上の社会人にコミュニケーションの指導をしてきたメンタルアップマネージャの大野萌子さんは、「自分では気がつかないうちに“マイナスの口ぐせ”が習慣化していて、周囲とのコミュニケーションに苦心している人が多く見られます」と話します。
「伝えたいことは同じでも、言葉遣いの違いでプラスに受け取られる場合もあれば、マイナスに受け取られてしまう場合も。相手に信頼感や安心感を与えて、好意的に受け取ってもらえるような表現を身につけていくことが大切です」(大野さん)具体的にどのような表現がマイナスで、どう言い換えるとプラスのメッセージになるのか、代表的な例を大野さんに教えてもらいましょう。
「は」と「も」を使い分ける「今日はかわいいですね」→「今日も素敵ですね」
いつもよりおしゃれしている女性を見て、「今日はかわいいね!」とひとこと。しかしこれは、相手に「いつもはかわいくないってこと?」と否定的に受け取られる可能性があります。「今日もかわいいね」と声をかければ、“いつもかわいいし今日もかわいい”というメッセージに。さらに、「かわいい」という表現には上から目線のニュアンスがあるので、「素敵」という言葉を使ったほうが、より好意的に受け取ってもらえるでしょう。
年齢や性別に関する発言は差別になる「若いのにしっかりしてるね」→「しっかりしてるね」
「若いのに~」という言葉には「若いから経験も知識も浅いはずなのに」というニュアンスがあり、褒め言葉でもエイジハラスメントと捉えられかねません。一方、注意するときに「いい年をして~もできないのか」という表現が使われることもありますが、これもエイジハラスメントです。褒めるときも注意するときも、年齢に関する発言は避け、シンプルに意見を伝えましょう。また、「女性なのによくがんばっている」「男のくせにこれもできないのか」などの性別に関する発言も差別につながるので、注意しましょう。
プライベートに踏み込む話題は禁物「結婚はしないの?」→「人生のプランはどう考えているの?」
「彼氏はいないの?」「結婚しないの?」「子どもはどうするの?」などの恋愛、結婚、出産に関する話題は、セクハラ発言につながりやすいものです。親しい関係性であればこうした話題で盛り上がる場合もありますが、そうでない場合は「プライベートにズカズカと踏み込んできた」と思われかねません。相手との距離感をきちんと認識することが大切です。
見た目の印象による思い込みを押しつけない「見かけによらず、すごいね」→「それができるなんて、すごいね」
一見おとなしそうな人が、大事なプレゼンで堂々とスピーチしている・・・そんなとき、褒めるつもりで「見かけによらず~」と発言することがあるかもしれません。しかしこれは、「そんなに仕事ができないように見えるけれど」という思い込みの押しつけだといえます。見た目だけで相手を決めつけず、そして思い込みを相手に押しつけずに、プラスの意見だけを伝えるといいでしょう。
こうした表現の違いを意識すると、人間関係を良好に保ちやすくなると大野さんはいいます。周囲に好印象を与えることができる言葉遣いを、取り入れてみてください。
安全運転アドバイス
安全な運転を確保するためには、車同士の円滑なコミュニケーションを図ることが重要なポイントの一つになります。カーコミュニケーションの方法としては、ウインカーによる合図など道路交通法等に基づくものと、ハザードランプによる停止の合図などドライバー同士で習慣的に行われている道路交通法に基づかないものがあります。今回は、これらの方法をまとめてご紹介します。
道路交通法等に定められている合図の時期や方法
相手の顔も見えず、言葉による伝達もできない運転時において、相手との円滑なコミュニケーションを図るためには、道路交通法等に定められたウインカー等による合図を的確に実践していくことが不可欠となります。
(1)合図が必要な場合
合図が必要な場合として道路交通法第53条では、「左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、または同一方向に進行しながら進路を変えるとき」と定められており、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならないとされています。
(2)合図の時期
合図はいつ出してもよいというわけではありません。なかには、右左折や進路変更の直前になってウインカーを出すケースも見られますが、これでは他車は対応しきれず事故につながりかねません。そのため、道路交通法施行令第21条において、合図を出す時期が次のように定められています。
①左折・右折・転回時
右左折又は転回しようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき。
②進路変更時
進路変更しようとする3秒前。
③徐行・停止・後退時
徐行、停止、後退を行うとき。
※徐行、停止は、制動灯が点灯することで、後退は後退灯が点灯することで合図とみなされます。
(3)必要以外の合図の禁止
右左折や進路変更など合図が必要な行為をしないにもかかわらず合図を出すのは禁止されています。
道路交通法によらないカーコミュニケーションの方法と留意点
(1)ハザードランプで減速・停止の意図を伝える
減速や停止をするときに、ハザードランプ(非常点滅表示灯)を点滅させ、後続車に自車の減速や停止を知らせるという方法が用いられることがあります。ハザードランプの点灯については、それが義務づけられているのは、「夜間に幅員が5.5メートル以上の道路に駐停車するとき」(道路交通法施行令第18条)と、「通学通園バスが、小学校の児童、生徒又は幼児の乗降のために停車しているとき」(道路交通法施行令第26条の3)であり、減速や停止時に関する規定はありません。ただ、特に高速道路では、渋滞の最後尾で停止しているときに後続車に追突されるという事故が発生していますので、最後尾に停止するときはハザードランプを点滅させて後続車の注意を喚起するのも事故から身を守るうえでの方法の一つといえるでしょう。なお、相手に道を譲られたときなどにハザードランプを数回点滅させる、いわゆる「サンキューハザード」は周囲の車に誤解を与えるおそれがありますから、控えたほうがよいでしょう。
(2)ポンピングブレーキで減速・停止の意図を伝える
停止するときに一気にブレーキを踏んで停止すると急停止になり、後続車に追突される危険が高まります。
停止するときは、ブレーキを一度に踏んで停止するのではなく、数回に分けて踏むポンピングブレーキを行い、後続車に停止する意思を伝えるようにするとよいでしょう。
(3)クラクションの使用はできる限り控える
交差点での信号待ちをしていて、信号が青に変わったにもかかわらず前車が発進しないときなどに、クラクションを鳴らして前車に注意を喚起するという方法が用いられることがありますが、自分では好意のつもりであっても、相手にそのように受け取られるとは限らず、トラブルの原因になることがあります。道路交通法第54条においてもクラクションの使用は限定されており、みだりに使用することは禁止されています。したがって、クラクションの使用はできるだけ控えるのが望ましいといえますが、やむを得ず使用しなければならない場合には、軽く短く鳴らすなどの配慮をするとよいでしょう。