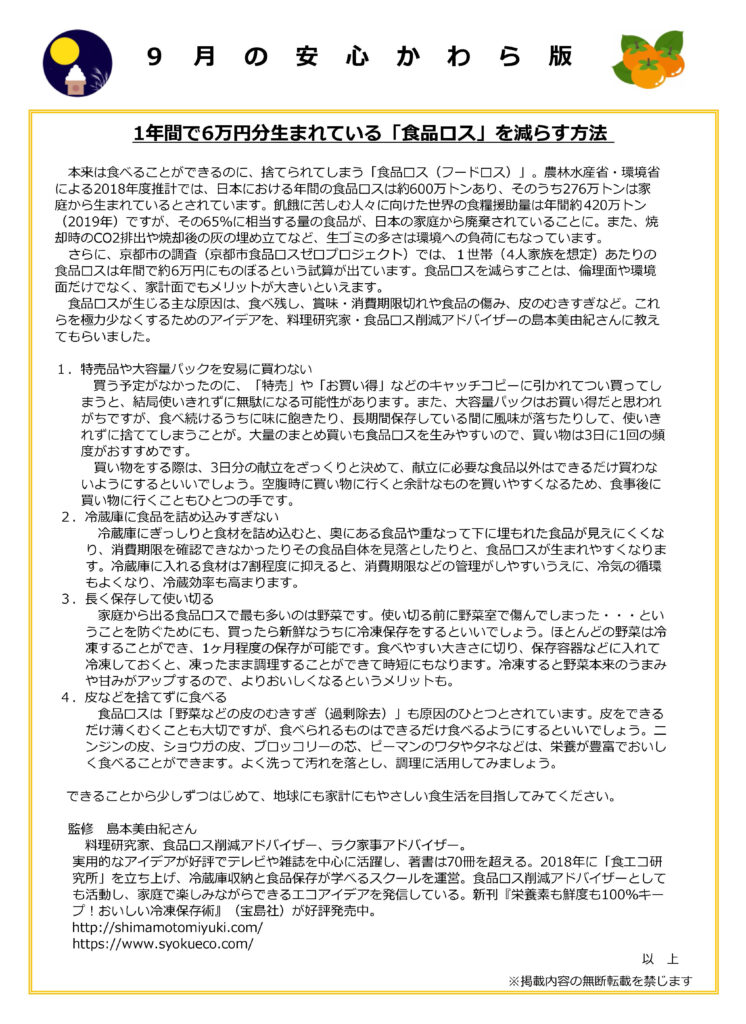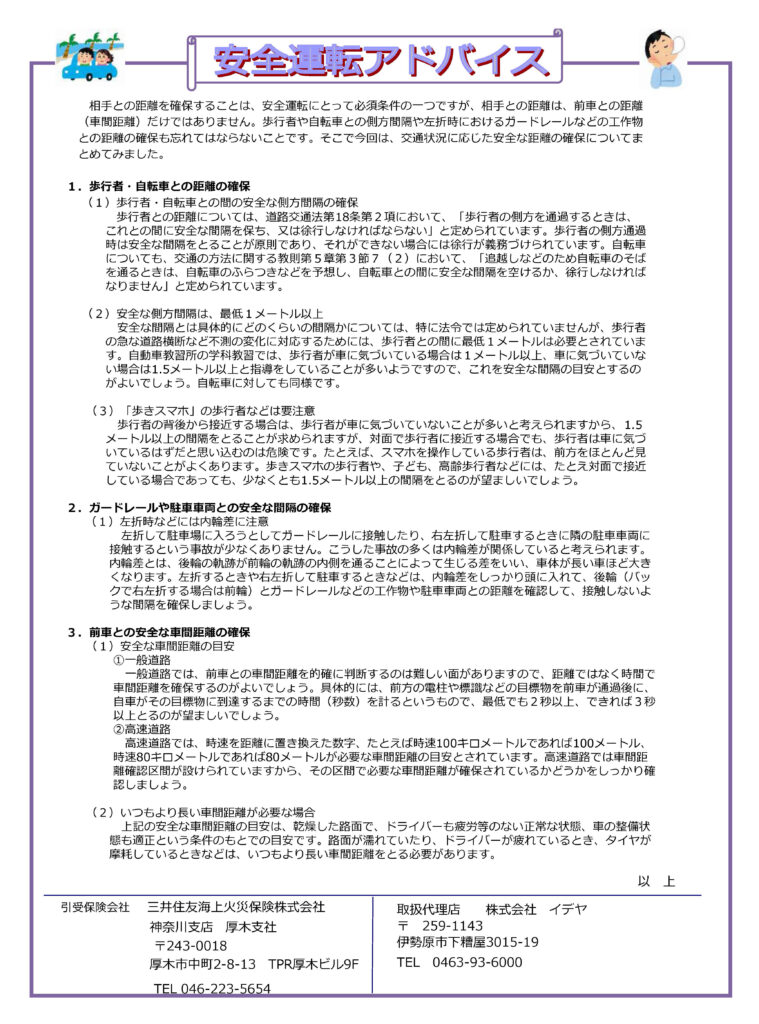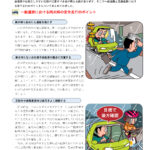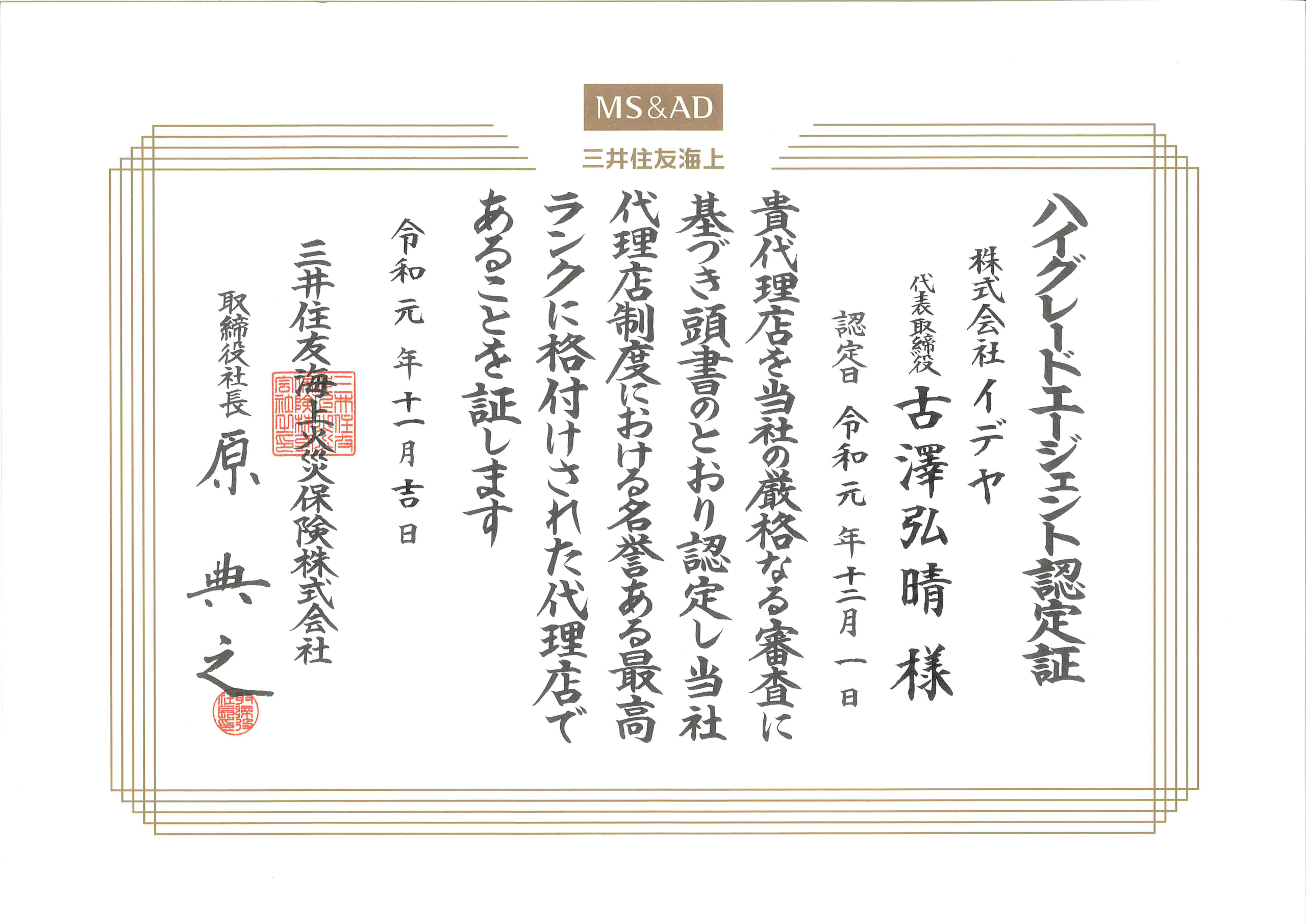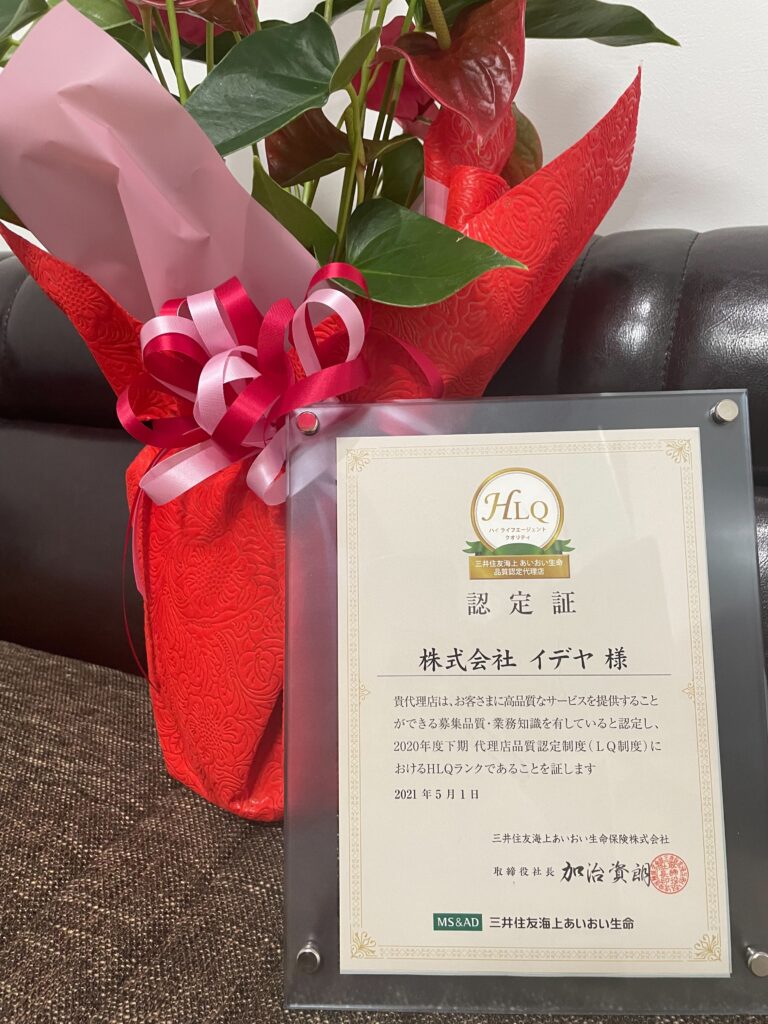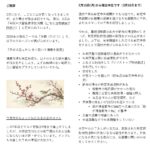9月の安心かわら版
1年間で6万円分生まれている「食品ロス」を減らす方法
本来は食べることができるのに、捨てられてしまう「食品ロス(フードロス)」。農林水産省・環境省による2018年度推計では、日本における年間の食品ロスは約600万トンあり、そのうち276万トンは家庭から生まれているとされています。飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量は年間約420万トン(2019年)ですが、その65%に相当する量の食品が、日本の家庭から廃棄されていることに。また、焼却時のCO2排出や焼却後の灰の埋め立てなど、生ゴミの多さは環境への負荷にもなっています。
さらに、京都市の調査(京都市食品ロスゼロプロジェクト)では、1世帯(4人家族を想定)あたりの食品ロスは年間で約6万円にものぼるという試算が出ています。食品ロスを減らすことは、倫理面や環境面だけでなく、家計面でもメリットが大きいといえます。
食品ロスが生じる主な原因は、食べ残し、賞味・消費期限切れや食品の傷み、皮のむきすぎなど。これらを極力少なくするためのアイデアを、料理研究家・食品ロス削減アドバイザーの島本美由紀さんに教えてもらいました。
特売品や大容量パックを安易に買わない
買う予定がなかったのに、「特売」や「お買い得」などのキャッチコピーに引かれてつい買ってしまうと、結局使いきれずに無駄になる可能性があります。また、大容量パックはお買い得だと思われがちですが、食べ続けるうちに味に飽きたり、長期間保存している間に風味が落ちたりして、使いきれずに捨ててしまうことが。大量のまとめ買いも食品ロスを生みやすいので、買い物は3日に1回の頻度がおすすめです。
買い物をする際は、3日分の献立をざっくりと決めて、献立に必要な食品以外はできるだけ買わないようにするといいでしょう。空腹時に買い物に行くと余計なものを買いやすくなるため、食事後に買い物に行くこともひとつの手です。
冷蔵庫に食品を詰め込みすぎない
冷蔵庫にぎっしりと食材を詰め込むと、奥にある食品や重なって下に埋もれた食品が見えにくくなり、消費期限を確認できなかったりその食品自体を見落としたりと、食品ロスが生まれやすくなります。冷蔵庫に入れる食材は7割程度に抑えると、消費期限などの管理がしやすいうえに、冷気の循環もよくなり、冷蔵効率も高まります。
長く保存して使い切る
家庭から出る食品ロスで最も多いのは野菜です。使い切る前に野菜室で傷んでしまった・・・ということを防ぐためにも、買ったら新鮮なうちに冷凍保存をするといいでしょう。ほとんどの野菜は冷凍することができ、1ヶ月程度の保存が可能です。食べやすい大きさに切り、保存容器などに入れて冷凍しておくと、凍ったまま調理することができて時短にもなります。冷凍すると野菜本来のうまみや甘みがアップするので、よりおいしくなるというメリットも。
皮などを捨てずに食べる
食品ロスは「野菜などの皮のむきすぎ(過剰除去)」も原因のひとつとされています。皮をできるだけ薄くむくことも大切ですが、食べられるものはできるだけ食べるようにするといいでしょう。ニンジンの皮、ショウガの皮、ブロッコリーの芯、ピーマンのワタやタネなどは、栄養が豊富でおいしく食べることができます。よく洗って汚れを落とし、調理に活用してみましょう。
できることから少しずつはじめて、地球にも家計にもやさしい食生活を目指してみてください。
監修 島本美由紀さん
料理研究家、食品ロス削減アドバイザー、ラク家事アドバイザー。
実用的なアイデアが好評でテレビや雑誌を中心に活躍し、著書は70冊を超える。2018年に「食エコ研究所」を立ち上げ、冷蔵庫収納と食品保存が学べるスクールを運営。食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、家庭で楽しみながらできるエコアイデアを発信している。新刊『栄養素も鮮度も100%キープ!おいしい冷凍保存術』(宝島社)が好評発売中。
http://shimamotomiyuki.com
https://www.syokueco.com
安全運転アドバイス
相手との距離を確保することは、安全運転にとって必須条件の一つですが、相手との距離は、前車との距離(車間距離)だけではありません。歩行者や自転車との側方間隔や左折時におけるガードレールなどの工作物との距離の確保も忘れてはならないことです。そこで今回は、交通状況に応じた安全な距離の確保についてまとめてみました。
歩行者・自転車との距離の確保
(1)歩行者・自転車との間の安全な側方間隔の確保
歩行者との距離については、道路交通法第18条第2項において、「歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない」と定められています。歩行者の側方通過時は安全な間隔をとることが原則であり、それができない場合には徐行が義務づけられています。自転車についても、交通の方法に関する教則第5章第3節7(2)において、「追越しなどのため自転車のそばを通るときは、自転車のふらつきなどを予想し、自転車との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません」と定められています。
(2)安全な側方間隔は、最低1メートル以上
安全な間隔とは具体的にどのくらいの間隔かについては、特に法令では定められていませんが、歩行者の急な道路横断など不測の変化に対応するためには、歩行者との間に最低1メートルは必要とされています。自動車教習所の学科教習では、歩行者が車に気づいている場合は1メートル以上、車に気づいていない場合は1.5メートル以上と指導をしていることが多いようですので、これを安全な間隔の目安とするのがよいでしょう。自転車に対しても同様です。
(3)「歩きスマホ」の歩行者などは要注意
歩行者の背後から接近する場合は、歩行者が車に気づいていないことが多いと考えられますから、1.5メートル以上の間隔をとることが求められますが、対面で歩行者に接近する場合でも、歩行者は車に気づいているはずだと思い込むのは危険です。たとえば、スマホを操作している歩行者は、前方をほとんど見ていないことがよくあります。歩きスマホの歩行者や、子ども、高齢歩行者などには、たとえ対面で接近している場合であっても、少なくとも1.5メートル以上の間隔をとるのが望ましいでしょう。
ガードレールや駐車車両との安全な間隔の確保
(1)左折時などには内輪差に注意
左折して駐車場に入ろうとしてガードレールに接触したり、右左折して駐車するときに隣の駐車車両に接触するという事故が少なくありません。こうした事故の多くは内輪差が関係していると考えられます。
内輪差とは、後輪の軌跡が前輪の軌跡の内側を通ることによって生じる差をいい、車体が長い車ほど大きくなります。左折するときや右左折して駐車するときなどは、内輪差をしっかり頭に入れて、後輪(バックで右左折する場合は前輪)とガードレールなどの工作物や駐車車両との距離を確認して、接触しないような間隔を確保しましょう。
前車との安全な車間距離の確保
(1)安全な車間距離の目安
①一般道路
一般道路では、前車との車間距離を的確に判断するのは難しい面がありますので、距離ではなく時間で車間距離を確保するのがよいでしょう。具体的には、前方の電柱や標識などの目標物を前車が通過後に、自車がその目標物に到達するまでの時間(秒数)を計るというもので、最低でも2秒以上、できれば3秒以上とるのが望ましいでしょう。
②高速道路
高速道路では、時速を距離に置き換えた数字、たとえば時速100キロメートルであれば100メートル、時速80キロメートルであれば80メートルが必要な車間距離の目安とされています。高速道路では車間距離確認区間が設けられていますから、その区間で必要な車間距離が確保されているかどうかをしっかり確認しましょう。
(2)いつもより長い車間距離が必要な場合
上記の安全な車間距離の目安は、乾燥した路面で、ドライバーも疲労等のない正常な状態、車の整備状態も適正という条件のもとでの目安です。路面が濡れていたり、ドライバーが疲れているとき、タイヤが摩耗しているときなどは、いつもより長い車間距離をとる必要があります。